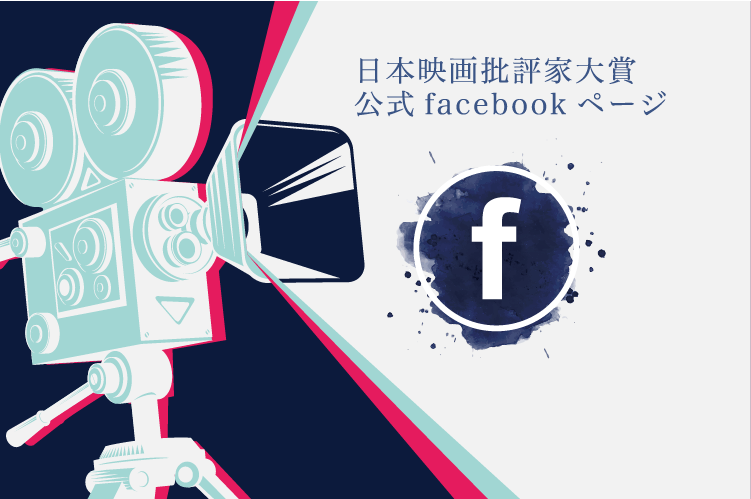新着情報
- お知らせ
「第33回日本映画批評家大賞」各受賞タイトル、授賞式開催のお知らせ
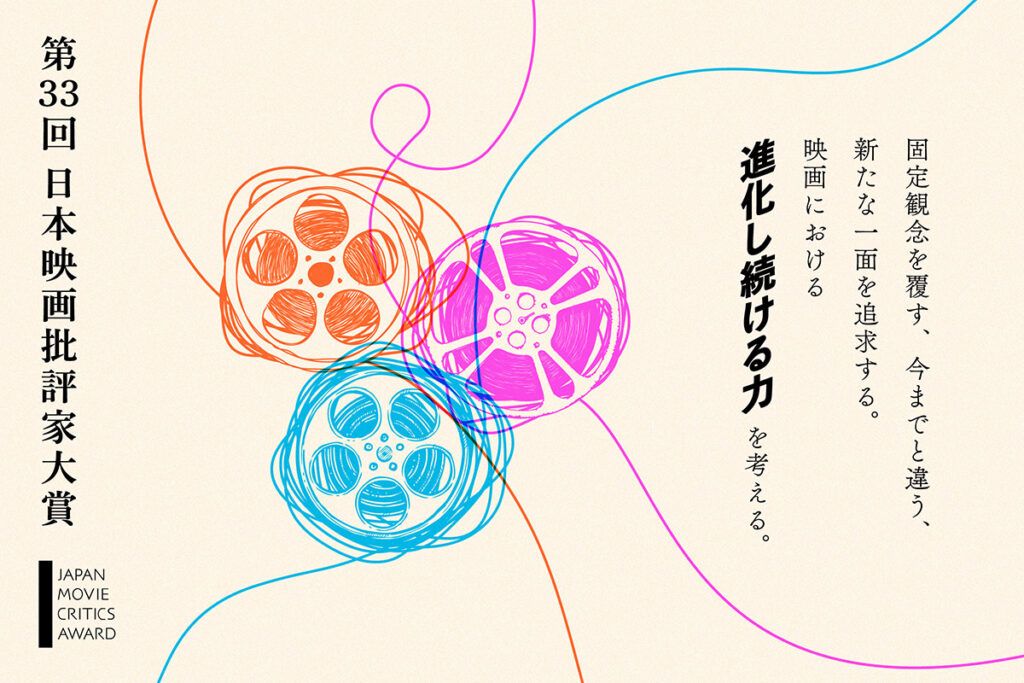
1991年に⽔野晴郎や淀川⻑治、⼩森和⼦といった映画批評家たちによって設⽴された『⽇本映画批評家⼤賞』。
今年もバラエティ豊かな⽇本映画作品のなかから、映画批評家たち選考員の独⾃の視点によって、厳密に選定した第33回⽇本映画批評家⼤賞の各タイトルを発表いたします。
映画批評家ならではの視点で選ばれる各賞に、映画ファンならずとも熱い注目をいただき、今年で33 年の歴史を数えるに至りました。本年度より選考委員に新メンバーも加わり、さらに新しい風が吹きこむバラエティに富んだ受賞作品・受賞者が揃いました。
受賞作品・受賞者
・青文字をクリックしていただくと、批評家コメントがご覧いただけます。
◎作品賞:『ほかげ』(塚本晋也監督)
◎監督賞:荻上直子監督『波紋』
◎主演男優賞:東出昌大『Winny』
◎主演⼥優賞:筒井真理子『波紋』
◎助演男優賞:磯村勇斗『月』
◎助演⼥優賞:新垣結衣『正欲』
◎ドキュメンタリー賞:『ライフ・イズ・クライミング!』(中原想吉監督)
◎アニメーション作品賞:映画『窓ぎわのトットちゃん』(八鍬新之介監督)
◎新⼈監督賞:金子由里奈監督『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』
◎新⼈監督賞:工藤将亮監督『遠いところ』
◎新⼈男優賞:アフロ『さよなら ほやマン』
◎新⼈男優賞:黒崎煌代『さよなら ほやマン』
◎新⼈⼥優賞:花瀬琴音『遠いところ』
◎脚本賞:上田誠『リバー、流れないでよ』
◎編集賞(浦岡敬⼀賞):今井大介『#マンホール』
◎撮影賞:芦澤明子『スイート・マイホーム』
◎松永文庫賞(特別賞):八丁座
◎ゴールデン・グローリー賞(水野晴郎賞):木野花『バカ塗りの娘』
◎ダイヤモンド大賞(淀川長治賞):小林薫『バカ塗りの娘』
第33回⽇本映画批評家⼤賞 授賞式
第33回目をむかえる日本映画批評家大賞の授賞式を今年も開催いたします。今年もこの特別なアワードをたくさんの映画ファンの⽅たちにご観覧いただけるように、授賞式典の会場にお越しいただけるチケットを販売させていただきます。

今年は「進化し続ける力」をテーマに授賞式を行い、映画愛が深く、軽妙洒脱な語り口で知られる松尾貴史氏をメイン司会に、神田れいみアナウンサーとともに各受賞者をお迎えします。

授賞式へ優先ご招待! 日本映画批評家大賞シネマクラブのご案内

日本映画批評家大賞には、映画ファンのみなさまがもっと映画を楽しめる会員「シネマクラブ」がございます。授賞式への優先ご招待や上映会イベントのチケット割引など、様々な特典をご用意しています。ぜひご登録ください。
批評家コメント
「これを撮らなければ」という信念を持った監督は今、日本に何人いるのだろうか。そう考えると塚本晋也監督は「監督」でありたいのではなく、「撮りたいテーマ」があるから監督をしているだけだ。自ら企画し、意思のまま執筆しカメラをまわすこの監督は、危機感から今、撮らなければならない映画だと、この『ほかげ』を生み出した。
テーマは「戦争と人間」。権力を持つことで人間の愚かさは露見されていくという最も恥ずかしい姿にだけ焦点を当てる。それを象徴するかのように冒頭、カメラははだけた女の白い脚を捉える。そのショットだけで、女が戦争により焼け野原となった世界で如何に生き続けてきたのか、観客に想像力を喚起させる。
そしてある時、飢えからこの家に辿り着いた少年と、性欲という衝動からこの家に赴いた青年という歪な家族が構成されていく。断片的な語りや表情、行動からうっすらと観客は彼らの生い立ちを理解していく。
映画は狭い家の中で展開され、ある瞬間、少年が外へ飛び出してから画は広くなり、趣里演じる女の主観から、まるで子を見守る母のような客観の視点へと変化を遂げる。そして戦後直後の世界を、子どもの立場から観客に擬似体験させてしまうのだ。
本作には感傷的なショットも演出もない。ただ淡々と「生き抜く」ために、自分より力のあるものに搾取され続けることを綴っている。これは監督の過去作『野火』と通ずるものがある。ずばり「戦争の恐ろしさ」だ。人は戦争が起こると人間の皮を被った野生へと姿を変え、欲望を満たそうと彷徨うが、それが続くと感覚は麻痺してしまう。
現実世界では悲惨なニュースを目にし続けながら、多くの人間が傍観している。そんな人間の冷酷さや無力さを本作では「男」と「女」として描いているのだが、見方を変えれば戦争を起こすことが可能な「政府」と「民間人」ともとれる。
本作の女に私たち民間人がならないようにするには、政治に関心を持つことであると塚本監督は映画を通して切実に伝えている。だからこそ今、『ほかげ』こそが、私たちが観なければいけない、伝えなければいけない映画だった。(伊藤さとり)
批評家コメント
荻上直子監督の名前を大きく羽ばたかせた『かもめ食堂』の影響もあると思うが、荻上監督作はどれもほっこりとした雰囲気を纏っている。そんなイメージを抱いている人は少なくないだろう。だからこそ『波紋』は「これまでと少し違うよね?」そんな声も聞こえてきた。
しかし、荻上監督は常に「解放」という共通のテーマを作品のなかに忍ばせてきた。『バーバー吉野』は、人それぞれ違っていいこと、声を上げること、変化を受け入れることを投げかけた。『かもめ食堂』は、国境を越えて自由と自立を手にする女性たちの生き方を示した。『彼らが本気で編むときは、』は、性差のもう一歩先に踏み込み家族を描いた。
その流れからすれば、『波紋』はよりストレートに「解放」を表現したといっていい。これまでの映画が纏ってきたやわらかなベールを自らはぎとったようなストレートな表現。家父長制の伝統や夫婦関係性といった、当たり前だと思い込んでしまっている日本社会の在り方に新興宗教問題を織り交ぜ、多くの人にとっての現実と映画の物語を地続きにしている。そうすることで、とても分かりやすく、とても力強いメッセージを放つ。
公式コメントで荻上監督が「私は、この国で女であるということが、息苦しくてたまらない」と記しているように、日本におけるジェンダーギャップ指数*は146カ国中125位、まだまだ男性中心の社会が続いている。そのなかで「異議あり」と立ち向かっていくような、道を切り拓いているような、そんな逞しさを荻上監督の作品、特にこの作品に強く感じる。オリジナル脚本で挑んでいる点も逞しい。
この映画のラストで、筒井真理子の演じる依子はフラメンコを踊る、激しく踊る。あの踊りは説明するまでもなく、依子の叫びを爆発させたもの、感情を具現化したものだ。まるでこれまでの作品のエネルギーが集約され放たれたような感動もある。そういう意味でも『波紋』は、荻上監督作のひとつ目の集大成といえるだろう。(新谷里映)
*ジェンダーギャップ指数:世界経済フォーラム発表による2023年度のスコア
批評家コメント
早逝したWinnyの開発者・金子勇の親族は、『Winny』で彼を演じた東出昌大の姿を見て涙したのだと伝え聞く。ふたりの外見は決して瓜二つなどではないのだが、生き写しのように見えたのだという。
だが、写真から外見を似せることはできたとしても、金子勇の姿を記録した映像や音声は(彼が著名人ではないため)ほとんど残っていないため、所作や声を似せることは難しい。そのため、東出はエンドロールにも使用されている記者会見の動画を繰り返し再生することで、人物像を作り上げていったのだと述懐。
Winny事件で誹謗中傷を浴びた金子勇と、自身のスキャンダルでバッシングされていた東出昌大の人生の岐路と岐路とが、奇遇にも『Winny』という映画によって交差したという不可思議がある。
そもそも、違法に<映画等の著作物>を共有させたWinnyという技術は、映画業界にとって目の敵であったため、開発者を擁護する本作は作品そのものが忌避されるような存在だという経緯もあった。
東出に限らず、著名人の中にはマスコミ報道などによってスキャンダラスな事象が表面化し、表舞台から姿を消した者たちがこれまでも沢山いた。
だが、どんな役を演じたとしても東出昌大という俳優はその役に近づこうとするし、「東出昌大は、東出昌大である」という唯一無二の個性が、映画そのものを輝かせる要素のひとつになる。
そう感じている映画監督たちがいるからこそ、彼は今なお<映画>に出演し続けているのである。斯様な<不屈の精神>を持つ人間と、斯様な<不屈の精神>に対して後方支援する人たちの姿。それは、映画が“作り物”だと分かっていても、わたしたちが金子勇と東出昌大の境遇とを重ねてしまう由縁なのだ。
だからこそ、彼が演じる金子勇像に対して、演技や役作りを超越した説得力を見出してしまうのである。俳優は、そんな役と一生のうちに何度も出会えるというわけではない。つまり、斯様な<一期一会>をわたしたちは目撃しているということなのだ。(松崎健夫)
批評家コメント
宗教問題はドキュメンタリーや劇映画などでも度々、描かれてきた。入信する人間の心理の根底には一体何が潜んでいるのか。この問題に斬り込んだのが荻上直子監督であり、どこにでも居そうな専業主婦の日常なのに、平静を保った表情で内に秘めた煮えたぎる感情を、その仕草や声の出し方で観客を魅力したのが「女優・筒井真理子」その人だ。
今までも『淵に立つ』や『よこがお』で数々の映画賞を受賞するなど演技力は既に証明されているが、美しく歳を重ね、親近感が湧く雰囲気を放ちながらも、どこかに綻びを感じる危うい女性を、彼女は演技で見事に生み出してしまう。
そんな筒井が『波紋』では、夫との間の愛の炎が消え、息子は自立し、一軒家で心に隙間風を感じる中で、いつの間にか新興宗教にハマってしまう専業主婦を流されるように演じているのが面白い。一般家庭の主婦(依子)が人との交流に小さな喜びを感じ、いつの間にか入信してしまう光景。映画では宗教活動が依子のサークル活動にさえ見えてくるのだ。その様子が滑稽であり愛おしくさえ感じるのだから不思議でならない。これはきっと監督の意図するところでもあっただろう。
昨今は女優という言葉も人により使い分ける時代だが、間違いなく彼女は「女優」だと個人的に思っている。依子のような「生きていく中で、母親を演じなければいけない女性の声に出せない叫び」を、筒井は全身全霊で表現できてしまうからだ。
劇中の夫に対する憎しみを隠す無表情だったり、宗教グループの勉強会での高揚した表情のコントラストから、彼女にとって家が居場所ではないことが分かってしまう。それでも彼女が唯一信頼する息子から恋人を紹介された時の憎悪に満ちた表情は、人間が社会で仮面を被って生きていることをまざまざと表現していた。
ラストカット、雨の中でフラメンコに身を投じる依子の名シーンは、筒井にしか表現できない「社会が求める姿に応えてしまう女の叫び」そのものだった。そんな女優・筒井真理子が魅せる女の複雑な感情を存分に味わいつつ、ブラックな女性讃歌である本作を堪能した。(伊藤さとり)
批評家コメント
この数年の磯村勇斗の成長ぶりには目を見張るものがある。昨年は本作『月』の他にも『渇水』や『正欲』といった、個性豊かな監督の話題作に相次いで出演。その存在感を際立たせることに成功した。
磯村勇斗は2015年、『仮面ライダーゴースト』のレギュラーに抜擢されたことを皮切りに、『東京リベンジャーズ』シリーズやしっとりとした『PLAN 75』などで頭角を現し、若手の実力派としての評価は急上昇。今回の日本映画批評家大賞では『渇水』と『月』の2作品で助演男優賞の候補に上がった。
『渇水』では、水道の「停水執行」という気の滅入る業務をそつなくこなす水道局員に扮し、平凡な男の平凡な姿を演じて、強烈な印象を残した。
一方、受賞の対象作品である『月』は、社会派ドラマである。その中で磯村は、理不尽のまかり通る重度障害者施設で献身的に働く青年が、いつしかゆがんだ正義感と使命感に取りつかれ、恐ろしい殺人者に変貌を遂げていく姿を、不思議な説得力を持って演じている。入院患者に読み聞かせをするための紙芝居の稽古に励む姿や、底意地の悪い先輩に小突き回されてニヤニヤする様子に、不気味なリアリティーが漂う。
入院患者に「あなたは心を持っていますか?」と問いかけ、殺人を正当化しながら次々に残虐行為をくり返す姿は、まるで役柄の“さとくん”に憑依されたかのようだ。磯村はいとも軽々と「理路整然とした狂気」という得体のしれない恐怖を具象化する。
まっすぐな澄んだ瞳が印象的な、市井の人から異常者まで、人間の陽と陰を軽々と演じ分けることの出来る俳優として、今後も息の長い活動を続けていくことは間違いない。
日本映画界の若手男優の地図が劇的に変化をしている今、磯村勇斗への期待は増々高まるばかりだ。(島敏光)
批評家コメント
脚本(台本)にどのような言葉が書かれていて、それをどのように解釈すればその“表情”になるのだろう。映画『正欲』の中で新垣結衣が見せる表情の数々はこちらに様々な問いを投げかけてくる、見事すぎるものだった。
朝井リョウによる同名ベストセラー小説を、稲垣吾郎と新垣結衣の共演で映画化した『正欲』。『あゝ、荒野』の監督・岸善幸と脚本家・港岳彦が再タッグを組み、家庭環境、性的指向、容姿など様々な想いを抱える人々が交差していくドラマだ。
新垣が演じた桐生夏月は広島のショッピングモールで働きながら実家で代わり映えのない日々を過ごしていた。夏月には周りに打ち明けていないとある欲があり、その欲を共有している唯一の人物である佐々木佳道(磯村勇斗)が地元に戻ってきたことを知り、再会を果たすのだが。
世の中の“普通”に入れなかった人の葛藤、そもそもその普通とは誰が決めるのか? 知らないうちにこちら側の普通を相手に求めすぎているということが、自分自身にもあるのではないか。夏月とエリート検事・寺井啓喜(稲垣)のやりとりを見ていると、心がざわざわと騒ぐ。新垣結衣演じる夏月の淡々としながら切実な語り口、寂しさと諦めと強さを秘めた視線が突き刺さり、「普通はこうだろう」「常識的に考えて」という自分の考えが、時には暴力となるということを考えさせられるのだ。
2001年のモデルデビュー以降、映画、ドラマ、CM、様々な媒体で華々しい活躍をし続けている新垣結衣。多くの人に愛されている女優であることは筆者がいうまでもないが、彼女の表現力はまだまだ計り知れない。もっともっと彼女の演技が見たい。そんな欲を駆り立ててくれる作品であった。(中村梢)
批評家コメント
上映期間も終わりかけ、観客も多くはなかったシネスイッチ銀座で今作を観た時、クライマックスで数人の客から拍手が起きたのをよく覚えている。
この作品はパラクライミングで世界選手権4連覇の記録を持つ、全盲のクライマー小林幸一郎(以下、コバ)と、彼の目となり、登る方向、手で掴み、足で踏む石の位置を下から指示するサイトガイドの鈴木直也(以下、ナオヤ)のバディドキュメンタリーである。
コバが面白い旅の予定ができたからその様子を短い動画で配信したいと、以前テレビで密着取材した中原想吉監督に声をかけた。中原監督は「それなら映画にしないか」と提案、今作が彼の長編監督デビュー作となった。
米ユタ州の奇岩フィッシャー・タワーズ。ふたりが目指すのは、自然がむき出した赤い砂岩の壁を垂直に登った先に突き刺さる、稲妻の形をした奇岩の尖塔だ。座布団一枚くらいのてっぺんに全盲のコバがひとりで登り、ひとりで立つべく進む。
地上カメラの他、一緒に登りながら撮影するクライミングカメラは、コバの一手も一歩も間違えられない緊張感を捉える。そしてそれすらも壮大な自然の一部にすぎないと思わせるロングショットをドローンカメラがおさえる。尖塔に向かう行程ではナオヤが観光写真でも見たことがない撮影アングルを中原監督に提案、我々は時にコバになり恐怖と快感を味わい、時にナオヤになりその情景を目に焼き付ける。
「こんなすごい事をやっていて、あんなすごい所に登った」だけの作品なら今賞の選考で満場一致にはならなかっただろう。当たり前に対等で、当たり前に個性を支えあい、信じ合い、笑い合い、人生の楽しみを探し続けると決めた人間たちの姿が、気持ちよくてたまらなかったのだ。そこは中原監督の観察眼と切り口の軽やかさなのだろう。センチメンタルにもベタな多様性ものにも、ヒーローものにもできた。だが中原監督が感じたままに、ストレートに描いてくれた。
観た者はそこから十分に「当たり前」に立ち戻るきっかけをもらえたはずだ。(安田佑子)
批評家コメント
黒柳徹子の幼少期を描くことで、子どもの個性を大切にするという教育方針に対する意義を考える。映画『窓ぎわのトットちゃん』が劇場公開された時、誰もがそういったことを主題にした映画なのだろうと想像したはずだ。
それは、1981年に発表された「窓ぎわのトットちゃん」という書籍が戦後最大のベストセラーになり、日本人であれば黒柳徹子という人物を誰もが知っていることによる、表層的なイメージがもたらした弊害だったように感じている。残念ながら本作は、興行的に大ヒットとなるような映画とはならなかった。それは即ち、版を重ねた「窓ぎわのトットちゃん」ほど、多くの人の目に触れることが叶わなかったということを意味する。
だからこそ、早期の再評価が必要だと個人的に焦燥しているのである。なぜならば本作は、何をおいても「今、観るべき映画」だったからだ。
本作は子どもの視点によって戦争に対して異を唱える、痛烈な反戦映画なのである。社会に戦争の影が忍び寄り、いつのまにか日常となってゆく不条理。突然、日常に劇的な変化が起こるのではなく、映画『窓ぎわのトットちゃん』ではシームレスに日常が変化してゆくプロセスを丁寧に描いている点が重要なのだ。
例えば、トットちゃんが通学で使う自由が丘駅の描写。改札の男性がいつのまにか女性になり、掃除をしていた男性も姿を消す。そう描くだけで、わたしたち観客は社会に軍靴の音が聞こえ始めたのだと理解するよう演出されているのである。
なにひとつ台詞では説明せず、映像だけで表現。それは、子どもが子どもなりに社会の状況を推し量ることを、観客に追体験させるという効果を生んでいる。また本作には、子どもにとってトラウマにもなりかねないような場面もある。ラストには希望もない。
だがそれは、あえてそうしたのだろう。そう描くことで、わたしたちは能動的に過去の歴史について考え始めるからだ。100年後の教科書に、2020年代が<戦前>などと記されないために。(松崎健夫)
批評家コメント
昨今、生きづらさを抱えている人々の物語を日本映画でも見られるようになった。そこには障がいや、ゲイなどのマイノリティ、貧困に苦しむ人々の姿が映し出されているが、本作では、目には見えづらい繊細な感情を持つ人々を見つめ、自然光や灯を活用し、心の色合いのように柔らかな世界を生み出していく金子由里奈監督の独創的でファンタジックな演出が光っていた。しかも感情をしっかり見つめながらも非現実的にならずに、最後まで心の機微から目を逸らさないのが彼女の映画だ。
この手法は『21世紀の女の子』での「projection」や『眠る虫』などでも特徴的で、金子監督が日常の些細なことにも目を向けていることや、現実と非現実の境界線の美しさも知っているから生まれる映像世界なのだろう。特に本作でのぬいぐるみや部屋の装飾からも、美術にも登場人物の人柄が見え、空間の居心地も含めて観客に伝わるものがあるから大切にしているようにも窺える。
それは劇中の音楽にもいえることで、ぬいぐるみサークルに集う人々の繊細な世界を壊さないよう音色が紡がれる。こんなにも細部の世界観にこだわった映画にはなかなか出会えない。しかも大前粟生の原作を兄と妹で脚本にすることで男女の視点も入れ、「男らしさ」や「女らしさ」の無意味さを検証していくのだ。
確かにぬいぐるみを大事にすることも八つ当たりすることも男女問わず、幼い頃私たちの多くがやっていた。さらに人にいえない感情をぬいぐるみに吐露することもあわせて、ある意味、ぬいぐるみの役割なのだと思い出させられた映画だった。
時には「辛いことがあったらなんでも話して」とSNSに書き込む優しい人々がいる。けれど、人に自分の悲しみや憎しみを話すことがその人の心の負担になるのでは、と考える人も世界には確実に存在する。この映画の彼らのように。
孤立せずに自分を守る方法を大事にする人との繋がりを描いた本作は、人との距離感がとても難しい昨今、しっかりと自分たちを取り巻く世界を見つめた演出により、間違いなく多くの若者の心に浸透していくだろう。(伊藤さとり)
批評家コメント
少女がコザの街を疾走する。
沖縄といえば、まっ青な海と白い砂浜に囲まれた南国の楽園。この映画ではヒリヒリするような沖縄が抱える現実を突きつけ、そんなイメージを根底から覆す。
コザの歓楽街。若きキャバ嬢がこともなげに「中学生でキャバ嬢は当たり前でしょ」と言い放つ。まるでドキュメンタリー番組を観ているような自然な仕草や言葉遣いがスクリーンから溢れ出す。喧騒を逃れ、帰路につくキャバ嬢として働く17歳のアオイ(花瀬琴音)の後ろ姿に哀愁が宿る。
アオイにはまだ幼い子供がいることがまもなく判明。ゆったりとしたテンポだが、ストーリーの展開は素早く、観る者を一瞬も飽きさせない。
「テーマというのは過程であって、答えではない」
自身の映画づくりに関してこう語るのはこの『遠いところ』を監督した工藤将亮である。今作が『アイム・クレイジー』『未曾有』に続く長編3作目。とてつもなく骨太の、一貫した眼差しは多くの選考委員の支持を得た。
全編沖縄での現地ロケを行い、徹底したフィールドワークにより浮かび上がらせた沖縄が抱える問題はとても重い。若年層のシングルマザー、DV、そして貧困だ。
美しい自然と沖縄でありながら海のないコザのうらぶれた路地、閉塞感に包まれた街を飛び出し、真っ青な海ではじける少女。警官に追われて逃げ回る少女。登場人物の喜怒哀楽をバランスよくチャンプルーして、悲惨でありながら躍動感にあふれる未熟な青春を、工藤監督は丁寧に描き出す。
脚本、監督を手がけたこの長編三作目となる本作で、工藤将亮監督はさらに評価を高めていくことになるだろう。自ら望まずして目の前に横たわる現実に向き合うしかない、少女たちの切実な現状をまざまざと描き出した。次はどんな作品を生み出してくれるのか、期待はいやが上にも膨らむ。(島敏光)
批評家コメント
宮城県石巻市の離島を舞台に、漁師の兄弟と東京から来た漫画家の奇妙な共同生活と家族の再生を描いた『さよなら ほやマン』は、不器用で優しい人間模様に笑いながら泣かされてしまう、あたたかいを超えたアツすぎる家族の話だ。
一人前の漁師を目指すアキラは船に乗ることができない弟のシゲルと2人暮らしで、津波で行方不明の両親と莫大な借金を抱えながらも、島の人々に助けられて生きている。上手くいきそうで上手くいかない、一難去ってまた一難、とままならない姿がなんとももどかしく、一歩外から見るとそれは辛い状況ではあると思うのだが、アキラとシゲルのくしゃくしゃの笑顔を見るとこちらが救われた気持ちになるのであった。それでいて「大変だけど、笑っていればなんとかなるさ」といった、無責任な楽観さだけにとどまることはなく、斬新な表現も使いながら物語が進んでいくところが見事だ。
アキラを演じているのはラップグループ「MOROHA」のメンバー、アフロ。映画初主演ということだが、その人間力に圧倒される。これまでもミュージシャン、所謂本業が俳優でない方々がスクリーンで見事な存在感をみせてくれたが、本作でのアフロのそれは別格だった。俳優もアーティストも同じ表現者という意味では同じなのであり、場合によっては俳優以上に“器用さ”を持ち合わせている存在なのかもしれない。しかし、アフロの声・表情は上手に作られたものではなく、アキラの言葉そのものとして観客の心にダイレクトに響く。「一歩踏み込んだ人間らしさ」が魅力的すぎるのである。
ネット上でのアフロ氏のインタビュー記事を読むと「アキラとしてリリックを作り、役柄に落とし込んだ」という言葉が出てくる。それらを読んでなるほど、こんなにアツい気持ちになれるのは、セリフとしてというよりも音楽のように感情に訴えてくるからなのだなあと納得したのだ。
余談だが、MOROHAのアフロ、UKの二人と筆者は同郷で同世代。このような素晴らしい表現者たちと同じ空を見ていたのだな、ということが誇らしくて仕方がないのである。(中村梢)
批評家コメント
面白い俳優が出てきた。目に力がある。宮城県にある小さな島が舞台の『さよなら ほやマン』は、冒頭からホヤ(海鞘)が喋り出す。「?!どんな映画?!」と思いきや、震災を経験した老若男女それぞれが優しさと思いやり、本音をぶつけあう、鑑賞後感が心地よい。庄司輝秋監督の商業長編デビュー作である。
今作で黒崎煌代(こうだい)は主人公兄弟の弟・シゲルを演じている。シゲルは島民たちに愛される天真爛漫さを持つが、シゲルが島の外に出れば「障がい者」にされ苛められると心配し、面倒を見る兄のアキラ(アフロ)は自分の夢を諦めている。そこに、訳ありの漫画家・美晴(呉城久美)が島にやって来て兄弟の日常をぶち壊していく。
シゲルにとってのある大きな決断を実行後、縁側で背中を丸め座りながら、顔をポリポリ掻き、「…一人前になりてーよ…」とぼやく場面。美晴との日々をトリガーに変わっていくシゲルの予定「不」調和な表情、セリフの間に目が離せなかった。影響を受けた人物が志村けん、藤山寛美、ディカプリオ、とインタビューで答えているのを読み納得もした。
黒崎は小さな頃から大の映画好きで、脚本を書いたり好きな映画のワンシーンを、鏡を見ながら演じていたという。2022年、インスタグラムで見つけた現在の所属事務所主催の俳優オーディションに5,000人の中から合格。その翌年に今作で本格的スクリーンデビューしたかと思えば、昨年暮れからNHK連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロイン・趣里の弟役に抜擢、「あの俳優は誰?」と全国の視聴者を騒つかせる存在となった。ここ2年の目まぐるしさに一番驚いているのは黒崎本人ではないだろうか。
太い眉とアーモンドのようにくっきりとした目。勇ましい武者絵にも、美しい京劇の女形にも変化(へんげ)できそうだ。「煌代」は煌めく時代を生きるよう願いつけられた本名だという。映画人として思い切り煌めいてほしいと願う。映画の中で生きることは、後の時代でも生きられることだから。(安田佑子)
批評家コメント
吸収力と理解力。花瀬琴音に表現力が備わっていることはもちろんだが、演じるための役づくりにおいて、その役に必要なものを吸収する力、吸収するために理解する力、花瀬のその能力はずば抜けている。
花瀬の演じたアオイは17歳。子供と大人の狭間であるこの年齢は、映画でもよく取り上げられる年齢だ。沖縄のコザで暮らすアオイが置かれた環境は、数ある17歳を主人公にした映画のなかでも、かなり過酷といえるだろう。アオイは17歳で、2歳の息子がいて、学校には行かずキャバクラで働いている。夫は仕事を辞め、暴力を振るうようになり、親を頼ることもできない。さらには大切な友人も失い……。過酷な現実が幾重にも重なり胸が苦しくなる。そんなアオイの人生を花瀬は見事に演じきり、十代の生きざまを投げかけてくる。一体どのようにアオイを演じたのか。
これはある名優に聞いたことだが、俳優にとって役とは、演じるものではなく生きることであり、生きるために必要なのは、実際にその役が置かれた状況で生活してみることだと。花瀬は初主演の映画ですでにそれを実践していた。彼女はアオイを演じるために、一カ月以上前から沖縄で生活し、若くして母になった人、キャバクラで働く人、シングルマザーの人に会い、話を聞いて過ごしたそうだ。アオイを構成するいくつものパーツがあり、そのひとつひとつのパーツに必要な情報を自ら探しに行き、出会った人たちを理解し、自分のなかに吸収してアオイのキャラクターに反映させていく。そんな作業だったのではないだろうか。
どのアオイの表情も印象深いが、一番の深みを挙げるとするなら、クライマックスの走りと泣き笑いにたどり着く。揺れるカメラワークのなかで彼女の感情を理解しようと必死になる、釘付けになる。シーンとしては明け方、顔はよく見えなくとも、それまでのアオイの表情が、感情が、走馬灯のように脳裏に映し出されていく。記憶に残る演技が、力強く刻まれていた。(新谷里映
批評家コメント
邦画・洋画問わず長年数々の作品が作られ、多くの映画ファンに愛されてきた“ループもの”。物語の中で登場人物が同じ期間を何度も繰り返すような設定を持つ作品のことを指し、実写のみならずアニメーションとの相性も良いジャンルだ。愛されてきたジャンルだからこそ、“目新しいストーリー”を作ることが難しいかと思われるのだが、2023年には『リバー、流れないでよ』という新たなループものの傑作が誕生した。
本作は、上田誠率いる人気劇団「ヨーロッパ企画」が手がけたオリジナル長編映画第二作。ヨーロッパ企画の拠点である京都・貴船の老舗料理旅館を舞台に、2分間のタイムループを描いたコメディー。
この2分間という「何にも出来なそうでちょっと動ける」絶妙な時間設定と、「以前の記憶は引き継がれる」という設定がドタバタを引き起こしていくのが何とも面白い。ヨーロッパ企画所属の藤谷理子による最高にチャーミングな芝居と、同劇団所属の俳優、バラエティ豊かな出演陣による“クセ強”キャラたちが「時間(タイムループ)から逃れられない人々」の焦燥を笑いに昇華させていく。
何よりも86分という短い尺の中で、最初から観客のハートをギュッと掴み、全く新しいループものを見せてくれる脚本が素晴らしい。本作の原案・脚本を手がけているのは、ヨーロッパ企画の主宰でもある上田誠。上田がこれまで脚本を手がけてきたのは『四畳半タイムマシンブルース』、『ドロステのはてで僕ら』といった“時間”をテーマにしたものや、『前田建設ファンタジー営業部』のように人間のチャーミングさを見事に描いた作品たち。「時間の面白さ」と「人間の面白さ」両方に好奇心を持って観たこともない作品を作り出す。
『リバー、流れないでよ』の魅力は上田作品の魅力とイコールといっても過言ではないであろう。今後もどのような作品が生み出されるのか、楽しみで仕方がない。(中村梢)
批評家コメント
『#マンホール』は、なぜか日本ではあまり作られてこなかった、限定された空間を舞台にした<ソリッド・シチュエーション・スリラー>というジャンル映画。
本作では、酔っ払ってマンホールに落ちた中島裕翔の一人芝居が作品の要となる。撮影の月永雄太は、シドニー・ルメット監督の『十二人の怒れる男』(57)に倣うかのように、限定された空間でありながら、ひとつとして同じ構図を用いないという映像を実践。
その多角的なアングルのショットを実践した撮影素材を駆使することで、編集の今井大介は限定された空間を映し出した映像にテンポやリズムを生み出しているのだ。
また、「半径数メートルのことしか描けていない」との揶揄を逆手に取りながら、マンホール内という物理的にも半径数メートルしかない限定空間によって、社会そのものを描こうと試みている。
同時に本作では、熊切和嘉監督が「カメラはマンホールから外に出ない」という愚直なルールも課している。そのため、電話をかけた相手の声色や漏れ聞こえる物音を情報に変換することで、中島演じる主人公だけでなく、観客もまた主人公と同じように電話の向こう側を<想像>するようになる。
つまり、編集によってもたらされた映像の<モンタージュ>が、音に対する<モンタージュ>をも導き、自ずと音に対しても敏感になってゆくのである。
さらに秀逸なのは、スマホが重要なモチーフであるにも関わらず、バッテリーの残量が減ってゆくことをピンチの理由にしないという点にある。残り僅かなバッテリーを気にする主人公の表情と、残量が表示されるスマホの画面とを交互に見せるような<モンタージュ>によって、危機感を煽るという演出を施すことができない。つまり、限定空間でピンチを描くための表現のひとつを、あえて作品から奪っているのである。
それでも、スマホの画面と中島裕翔の表情による<モンタージュ>を基本にしながら、作品に漂う緊張感を構築。いっけんシンプルながら、熟考された編集技法の数々が『#マンホール』には指摘できる。(松崎健夫)
批評家コメント
80本以上。芦澤明子が撮影した映画の本数だ(撮影協力も含む)。その数に驚く。キャリア30年。もう一度、驚く。近年は、撮影部や照明部、録音部など各部署で女性の比率が高まってきているものの、芦澤がその先駆者であることは間違いない。
ジャン=リュック・ゴダール監督の『気狂いピエロ』を観て映画の世界を目指し、助監督、撮影部を経て、平山秀幸監督の『よい子と遊ぼう』(94)で撮影監督として劇映画デビュー。キャリア30年、80本という数のなかには、黒沢清監督の一連の作品をはじめ、原田眞人監督、深田晃司監督、沖田修一監督、大友啓史監督、一昨年にはインドネシアのエドウィン監督との仕事もある。映画の規模もジャンルもさまざま、その幅の広さも芦澤の強みだ。
撮影賞を受賞した『スイート・マイホーム』は、斎藤工が監督だ。撮影は「芦澤さんでいきたい」と指名だったという。芦澤の技術、そしてこの作品がホラーであることも、彼女に白羽の矢を立てた理由のひとつなのではないかと想像する。公式コメントで、芦澤は「何でもない日常の延長線上に潜んでいる心の闇や有り様を、断定することなく描きたかった。特に闇の表現には気を使った」と語っている。闇=黒、ホラーは特に黒色が重要なジャンルであり、彼女がとりわけこだわってきた黒色を最大限に活かせる題材でもあっただろう。実際、人間の心の闇とスクリーンに映し出される黒色が物語のスパイスになっている。
また、本作のメインロケーションは一軒家。撮影は取り壊しが決まっているモデルハウスを借りて行われた。その一軒家のなかに“あの空間”が作られたわけだが、こんなにも限られた狭い空間で、どうやって撮影をしたのか? という関心と驚嘆。しかもこの映画、俳優たちの顔のクローズアップが多い。撮影技術はもちろんのこと、いかに台本の深いところ、俳優の演技の奥まで捉えているかが鍵となる。感情を撮る、感情を映す、それが真の撮影なのだと思い知らされた。(新谷里映)
批評家コメント
第33回の特別賞にこれほど相応しい受賞者はいない。広島市のまさに中心地・八丁堀の象徴ともいえる福屋デパートに居を構える映画館「八丁座」だ。
“進化し続ける力”をテーマに掲げる今回、この八丁座には強烈に、自らを信じ進む意気込みと、それを実現するマンパワーを感じた。
郊外型の大型シネコンにも翳りがみえる昨今、大資本がなくとも「映画館」は永久不滅だと肌身で感じさせてくれる八丁座には心底驚かされた。福屋の一角、エレベーターが開いた時から非日常の空間が観客を迎える。細部にまでこだわった和モダンの粋で美しい装飾。そしてスクリーンでは優しい木の温もりとベルベットの、広々とした特注シートが我々を優しく包み込んでくれる。1本の映画を鑑賞するのに、期待はいやが上でも膨らむ。
爆心地からほど近かった福屋も建物外廓を残して内部全焼だったというが、復興開始間もなく、この場所で映画上映が行われたという。復興へと向かう市民にとって、映画はまさしく希望の灯だったのだろう。
その広島の街なかから2009年、映画館がなくなった。「この街から映画の灯を消していいわけがない」。八丁座を運営する(株)序破急の蔵本順子社長と住岡正明総支配人には、確固たる信念があったという。周りの大反対を振りきってでもこの劇場を産み出した。それも江戸時代の芝居小屋を模した独特の劇場空間。当時の彼らの想いが、今、広島の街っ子の贅沢な日常の映画体験につながっている。映画館を後にする観客たちの満足げな顔にそれはまざまざと表れていた。
その土地に根ざした映画館の在り方があるのではないか。映画とともに再生と復興を遂げてきた広島。この街の人々とずっと共にあった映画。八丁座からは、溢れる広島愛とともに、街と共に映画館も進化していける、という希望をもらえるはずだ。きっとこれからも、この場所で灯る映画は多くの人の人生を豊かに彩ることだろう。
半被を翻しながら、お客さまと活き活きと交流するスタッフたちの姿が、とびきり粋で格好よくみえた。(日本映画批評家大賞機構事務局)
批評家コメント
50年キャリアを重ね、挑み続ける女優・木野花にゴールデン・グローリー賞を贈ることができるのは光栄だ。74年に女性だけの劇団「青い鳥」を創立、舞台俳優としてキャリアをスタートし、演出にも加わりながら小劇場ブームのど真ん中にいた。この仕事に真っしぐらかと思いきや、演劇を数年やったらさっさと青森に帰り前職の教師に戻ろう、55歳までに辞めて何かの職につこう、と思っていたらしい。その後「歳を重ねると自分がどんな風に変わっていくのか見てみたい」と思えるようになったという。
その思いからか、近年の木野の役は尖りまくっていた。『愛しのアイリーン』では、息子がフィリピンから連れてきた嫁に執拗なまで悪態をつく姑役。『波紋』では失踪して戻ってきた夫のことで悩むヒロインに「…殺(や)っちまう?」と不敵に提案するパート先の同僚役。『ヴィレッジ』に至ってはセリフがなく読み取れない能面のような表情、トレードマークのメガネをとり、老けメイクで演じた一族の女当主役。どれも強烈な存在感だった。
かと思えば、今回の青森・弘前を舞台にした鶴岡慧子監督『バカ塗りの娘』では、どこまでも温かい距離でヒロイン家族と接する「吉田のばっちゃ」役だ。私たちは、近作で木野の演技に怯えたことを忘れて、ばっちゃが好きになっている。ヒロイン美也子(堀田真由)が家に駆け込んでくれば、ばっちゃはご飯を作る。その腰が少し曲がった後ろ姿がどこか懐かしい。祖母ではない近所のばっちゃらしく、美也子の家族に踏み込み過ぎず思いやるその距離感が見事だ。青森出身の木野の語り口に、津軽弁がとても優しく柔らかく耳心地よい言葉だということも教えてくれる。
作品のタイトルにもある「バカ塗り」は、完成までの工程がバカみたいに多い津軽塗のこと。おこがましい願いだが役者・木野花はまだ完成しないでほしい。尖って丸まって狂って寄り添って笑って泣いて。
今後も人間の持つ機微を丁寧に塗っては研ぎを繰り返す、バカ塗りのような役者でいてほしい。(安田佑子)
批評家コメント
だれからも信頼される役者がいる。
2023年に公開された『バカ塗りの娘』のキャッチ・コピーは、――ひたむきに塗る。ひたむきに生きる―― ヒロイン(堀田真由)の父親で、津軽塗り職人役を演じるのが小林薫。今作では、その長いキャリアで培ってきた役者としての本分を全うするかのような父親像を見事に演じていた。
小林薫とはまさに、ひたむきに芝居に取り組んできた職人のような俳優である。
1971年に唐十郎の主催する「状況劇場」に所属。そこは紅テントと呼ばれ、寺山修司主催の「天井桟敷」と人気を二分する過激なアングラ演劇集団で、李麗仙、麿赤児ら、個性的な名優怪優が名を連ねていたことでも知られている。
小林薫もその一人で、退団の際には、それを阻止するために唐十郎が出刃包丁を持って彼のアパートに乗り込んだという逸話もある。アングラ業界でもそれだけ期待されていたということだ。
1977年に『はなれ瞽女おりん』で映画デビュー。その後も『それから』や『東京タワー~オカンとボクと、時々、オトン~』などの良質な作品に出演し、堅実な演技を披露。
それが主役だろうと、小さな役柄であろうと、小林薫という俳優は染み入るように、ごく自然にスクリーンと馴染んでしまう。特に息の長いシリーズである『深夜食堂』でみせた、その表情ひとつで語り、演技を成立させてしまう姿に、役者としての円熟と洒脱さを感じた。
『バカ塗りの娘』でも津軽弁を見事にあやつり、気の遠くなるような作業をくり返す津軽塗り職人の気むずかしさ、素朴さ、不器用な優しさを身に纏い、若いヒロインを悠然と包み込む。単調な作業の合間に、娘と二人で無言でアイスクリームを食べる、ほんの一瞬ののどかなシーンさえ深く心に残る。
スクリーンになめらかに溶け込み、唯一無二の存在感を漂わせ、これからも小林薫は数々の名作やエンタメ作品を支え続けていくことだろう。(島敏光)
授賞式への登壇決定者一覧
登壇決定者
作品賞:『ほかげ』 塚本晋也監督
監督賞:『波紋』 荻上直子監督
主演男優賞:『Winny』 東出昌大
主演女優賞:『波紋』 筒井真理子
助演男優賞:『月』 磯村勇斗
助演女優賞:『正欲』 新垣結衣
ドキュメンタリー賞:『ライフ・イズ・クライミング!』 中原想吉監督
アニメーション作品賞:映画『窓ぎわのトットちゃん』 八鍬新之介監督
新人監督賞:『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』 金子由里奈監督
新人監督賞:『遠いところ』 工藤将亮監督
新人男優賞:『さよなら ほやマン』 アフロ
新人女優賞:『遠いところ』 花瀬琴音
脚本賞:『リバー、流れないでよ』 上田誠
編集賞:『#マンホール』 今井大介
撮影賞:『スイート・マイホーム』 芦澤明子
松永文庫賞:八丁座
ゴールデン・グローリー賞:『バカ塗りの娘』 木野花
ダイヤモンド大賞:『バカ塗りの娘』 小林薫
登壇調整中
新人男優賞:『さよなら ほやマン』 黒崎煌代