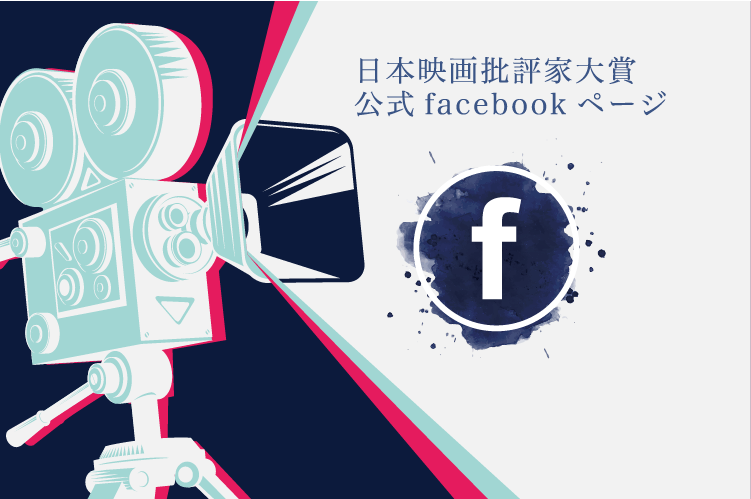新着情報
- イベント
『第32回日本映画批評家大賞』授賞式が開催されました

2023年5月16日(火) 東京国際フォーラム(ホールC)にて、第32回日本映画批評家大賞の授賞式を開催させていただきました。
数ある国内の映画賞のなかでトリを飾る日本映画批評家大賞。選考委員たちにより厳正な審査のうえ選ばれた、2022年に際立つ活躍をみせた豪華な方々が授賞式にご登壇してくださいました。
フレッシュな新人各賞から、技術賞、そしてベテラン俳優までが勢ぞろい。またサプライズゲストもお越しいただき、映画愛溢れる授賞式となりました。
司会には昨年に引き続き、自他ともに映画好きで知られる笠井信輔アナと茅原ますみアナ、ご夫婦でマイクをとっていただきました。「映画人が映画人に贈る賞」というモットーにふさわしい、映画愛あふれるトークによって会場が満たされました。
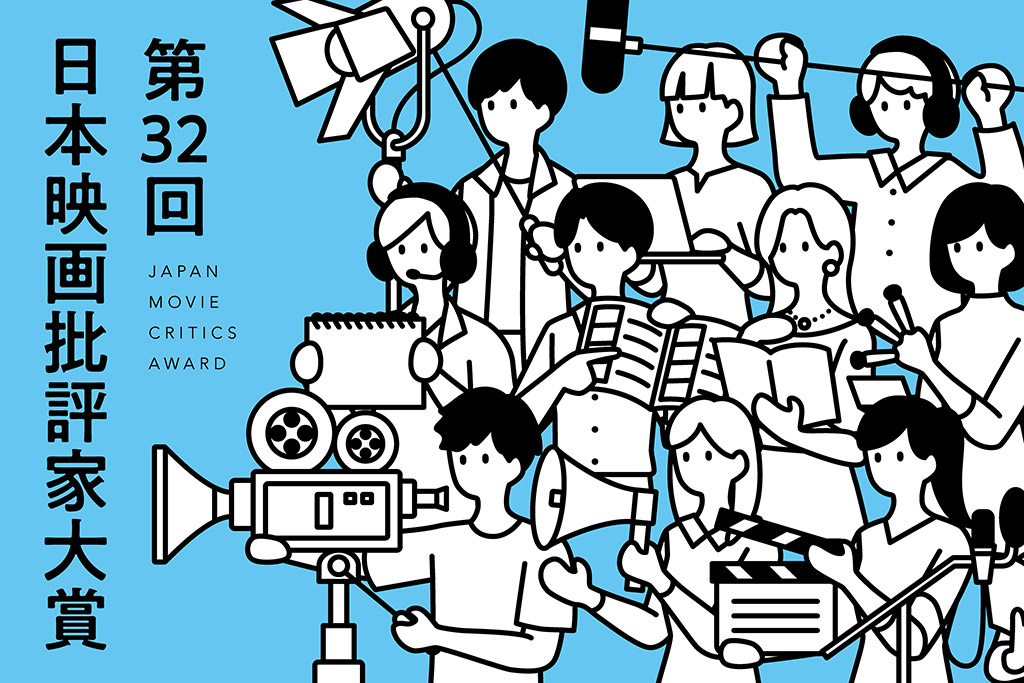
第32回は、それぞれの映画作品がもつ『作品のチカラ』をメインテーマに、各受賞者・受賞作品にふさわしいタイトルを選考委員たちが表現しました。
受賞作品・受賞者 一覧
青文字をクリックしていただくと、批評家コメントがご覧いただけます。
◎作品賞:『メタモルフォーゼの縁側』(狩⼭俊輔監督)
◎監督賞:三宅唱『ケイコ ⽬を澄ませて』
◎主演男優賞:中井貴⼀『⼤河への道』
◎主演⼥優賞:板⾕由夏『夜明けまでバス停で』
◎助演男優賞:窪⽥正孝『ある男』
◎助演⼥優賞:吉岡⾥帆『島守の塔』
◎アニメーション作品賞:『夏へのトンネル、さよならの出⼝』(⽥⼝智久監督)
◎アニメーション監督賞:湯浅政明『⽝王』
◎ドキュメンタリー賞:『夢みる⼩学校』(オオタヴィン監督)
◎新⼈監督賞:⽵林亮『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』
◎新⼈男優賞(南俊⼦賞):坂東⿓汰『フタリノセカイ』
◎新⼈⼥優賞(⼩森和⼦賞):伊東蒼『さがす』
◎脚本賞:吉⽥恵輔『神は⾒返りを求める』 ※吉田恵輔の吉はつちよしが正式表記
◎編集賞(浦岡敬⼀賞):⼩林譲 ⽵林亮『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』
◎ワタシタチのトキワ荘賞:一般財団法人手塚治虫文化財団
◎特別賞(松永武賞):⽴川志の輔『⼤河への道』
◎特別主演男優賞:岡⽥准⼀『ヘルドッグス』
◎ゴールデン・グローリー賞(⽔野晴郎賞):⾵吹ジュン『裸⾜で鳴らしてみせろ』
◎ダイヤモンド⼤賞(淀川⻑治賞):宮本信⼦『メタモルフォーゼの縁側』
批評家コメント
とても温かく、前向きな映画である。そして登場人物たちの深厚な感情を丁寧に映し出している映画でもある。
昨今、日本映画は人気漫画の映画化が多く、この『メタモルフォーゼの縁側』もその部類に入るが、人気のある若手俳優に光を当てた青春映画の登竜門的な映画とは異なり、17歳の女子高生の青春、75歳の老婦人の青春をとおして、人生における気づきを描いている。
しかも、漫画原作であることを最大限に活かし、漫画を創り出す者=作家の苦悩も主人公2人の物語にそっと寄り添わせる形で描いている。
118分、物語の展開はとても緩やかである。世界的に注目されている漫画という日本カルチャーを題材に、BL(ボーイズ・ラブ)という漫画のジャンルで多様性に触れながら、周囲に馴染めず将来が決まらない学生の葛藤、母子家庭や老人のひとり暮らしなど、現代社会の片隅に生きる人たち、市井の人たちを映し出す。
絢爛豪華なCGやアクションを多用した映画とは対極に位置する映画であるため一見平淡に映るかもしれないが、小さなものを大きな尺で描くことも映画的だ。
脚本・岡田惠和と監督・狩山俊輔の組み合わせも、この作品にとって理想的だったのではないか。数多くのドラマや映画の脚本を手がけてきた岡田惠和の優しさに満ちた脚本を、映画監督としては今作が3作目となる狩山俊輔が俳優の演技と融合させていく。
17歳のうらら、75歳の雪、この2人の感情を最初から最後まで誠実にすくい取る。他を描きすぎずに2人の物語として走りきったことを評したい。
うららと雪を演じた芦田愛菜と宮本信子の配役も素晴らしい。祖母と孫ではなく、年の差58の“友情”がどこか羨ましくもあり、互いに刺激を受けて、その刺激がより良い未来を描き出す。
映画はさまざまな世界を映し出すことができ、その世界を通じて伝えるべきものがある。『メタモルフォーゼの縁側』は温かさと前向きさを伝える映画。いまこの時代に必要な映画である。(新谷里映)
批評家コメント
今も昔も、映画は監督で観る、と語る映画ファンが数多く存在する。そんな人たちから今、最も注目を浴びているのが三宅唱監督ではないだろうか。
1984年に札幌に生まれ、将来の目標の定まらなかった少年が「映画の中には何でもある」と気付き、映像の世界にのめり込んでいく。三宅唱は地元の高校を卒業後に上京、映画美学校に通いつつ、一橋大学に学び、現在までに長編・短編あわせ20本近くの作品を残している。
その中でも『Playback』は「映画芸術」誌の日本映画ベストテンの第三位。『きみの鳥はうたえる』では伸び盛りの俳優陣から見事な演技を引き出し、繊細な青春ドラマに仕上げ、高い評価を受ける。
『ケイコ 目を澄ませて』では、実在した聴覚障害の女性プロボクサーをモデルにして、新しい物語を紡いでいく。セコンドの声もレフェリーの声も聞こえないというとんでもない逆境の中でファイトを続けるヒロイン(岸井ゆきの)の、まさに野獣のような表情は決して忘れることが出来ない。役者の本気を引き出す監督の手腕は恐るべしだ。
この物語は、従来のボクシング映画にある挑戦、敗戦、挫折、再挑戦、勝利、感動という王道の方程式から遠く掛け離れているが、その迫力と感動は、どのスポーツ映画より深く心地よい。
『きみの鳥はうたえる』では無目的に日々を過ごす若者を、『ケイコ 目を澄ませて』では一つの目標にダイナミックに突き進むハンディを抱えたアスリートの姿を描き、ベクトルの違う二つの青春をきめ細やかに描き分けている。本作では力強さと繊細さを同居させ、主人公が聴覚に障害を抱えていることとは裏腹に、観客は様々な音を耳にする。町の雑踏、生活音、ジムのざわめき、そしてグローブが作り出す音。16mmフィルムで撮影されたなめらかな映像と相まって、緊張感を高めていく。
三宅唱の名前を見つけたら、何はともあれ映画館に直行することをおすすめする。(島敏光)
批評家コメント
この俳優が出ているのであれば、観てみたい。中井貴一は、そう思わせてくれる国民的俳優である。デビュー作『連合艦隊』に始まり、『ビルマの竪琴』『四十七人の刺客』『マークスの山』『梟の城』『壬生義士伝』など数多くの映画に主演・出演。2007年の主演映画『鳳凰 わが愛』ではプロデュースも手がけた。
今や、世界的には俳優が監督や製作を兼ねることは珍しくはないが、日本映画界においてはその数は少なく、しかも日本・中国合作の映画で主演とプロデュースを兼ねたことは、当時、話題になったと記憶している。
中井貴一のフィルモグラフィを見ると時代劇の数が多い。時代劇に求められる俳優であることはもちろん、彼自身が時代劇を自身のキャリアに取り入れてきたともいえるだろう。それは、今回の主演男優賞となった映画『大河への道』に対する取り組み方からも察することができる。
『大河への道』の原作は、立川志の輔による新作落語「大河への道-伊能忠敬物語-」。“究極の話芸”とも評され、中井貴一も魅了された一人だ。その面白さと素晴らしさを「自分は裏方でもいい、何としても映画にして届けたい」と自ら企画。
さらには「このままでは時代劇にまつわる文化が日本から消えていくかもしれない……」と危惧していた中井にとって、時代劇というジャンルも重要なポイントだった。
『大河への道』では、伊能忠敬の大河ドラマを成立させるために奮闘する現代パートと、伊能忠敬亡き後に地図を完成させるため奔走する弟子たちの江戸時代パート、二つの時代の物語が展開し、主要キャストは二つの時代それぞれで役を演じている。
中井が演じた市役所の池本、地図作りの完成を見守る江戸幕府の高橋景保、どちらの役にも共通するのは、情熱と誠実さ。中井貴一という俳優にもそれはぴたりと重なる。日本映画の未来に、時代劇という希望を映し出す映画をよくぞ作ってくれた、演じてくれたと、感謝を込めて主演男優賞を贈りたい。(新谷里映)
批評家コメント
凜とした女優である。板谷由夏の持つ美しさの中には、他の美人女優にはないある種の生活感が息づいている。
高橋伴明監督による『夜明けまでバス停で』では、コロナ禍で住み込みの居酒屋の仕事を失い、街の中に放り出され、ファミレスや漫画喫茶に通うお金にも事欠き、遂には人けのないバス停で一夜を過ごすことになる女性に扮している。
どこにでもいそうな正義感にあふれるごく普通の女性。寒々しい明かりのポツンと灯るバス停のベンチで仮眠を取る姿は、何とも切なく痛々しい。板谷由夏は心の中に怒りを秘め主人公になり切る。そのリアリティーにあふれる佇まいが、物語をグイグイと引っぱっていく。
1975年、福岡に生まれた板谷由夏は、バランスの良い体型と長身を生かして、10代の後半からモデルとして活躍する。1999年『avec mon mari』で映画デビュー。この会話のあふれ返るドラマで、いきなりヨコハマ映画祭の最優秀新人賞に輝く。2000年代に入ってからは『運命じゃない人』『サッド ヴァケイション』などのエッジの利いた作品で高い評価を受ける。
テレビドラマにも数多く出演。2007年からは、11年間の長きにわたって「News Zero」のキャスターを務める。ファッション・ブランドのディレクターでもある。
才気あふれる女優でありながら、まるでどこかで会ったことあるような気にさせる雰囲気も持ち合わせている。本作のヒロインはホームレスに転落して、ゴミ箱の食品をあさるまでになっても、プライドを捨て切れず、人に頼らず、物乞いもせず、体も売らない。板谷由夏はそんな社会から孤立した女性にぴったりと寄りそう。役作りのために居酒屋でバイトをしたという逸話も残っている。
柄本明、筒井真理子(ルビー・モレノもいる!)という曲者俳優に囲まれ、物語の中心にデンと腰を据え、圧倒的な存在感を見せつける。
数々の強敵を打ち破って、今回の日本映画批評家大賞の主演女優賞となった。(島敏光)
批評家コメント
石川慶監督作品『ある男』で窪田正孝が演じたのは、幾重にも重なる心の傷を封じ込め、他人として生きることを選んだ男という難役だ。
映画冒頭、傘を畳み、街の文房具店に入ってきたその男は、雨雲まで店内に連れてきたかのような空気を纏っている。男は店番の里枝(安藤サクラ)が気になっているようだ。関わってはいけない危ない男なのか、ただ引っ込み思案なのか謎めいていてわからない。
谷口大祐と名乗ったその男(その後X=エックスと呼ばれる)は、のちに里枝と結婚。勤勉に仕事をし、妻と子供たちにも愛情深い男として、物語の序盤で死んでしまう。だが死後も窪田の存在感は作品の最後の最後まで漂い続ける。
今作では窪田正孝のキーパーソン力がしっかりと光った。彼がスクリーンに登場すると、何かやらかすのか、ただ静かに相手に寄り添うのか、善人か悪人か予想がつかず、それが物語を牽引する。それも力ずくではなく、とても自然に。
今回、他人の出自で生きた男を演じるにあたり、窪田は「役を埋めず、Xのグレーゾーンをそのままにした」と言う。さもすると観客にわかりやすく、Xの事情を理解してほしいと俳優の欲が一瞬の演技に出てしまうところを、窪田はXのささやかな欲望に純粋に従った。そしてこのXという男の評価を、遺した妻や息子(坂元愛登)、Xの身元調査を依頼される弁護士(妻夫木聡)、そして観客に委ねた。
Xはある者が見れば不幸で、ある者が見れば幸せだろう。また、短いシーンだがXの父親役も窪田が演じ、Xとは両極端な息子への愛情表現で強い印象を残した。
今年はすでに公開された『湯道』では助演、今後公開される斎藤工監督作品『スイート・マイホーム』では主演、瀬々敬久監督作品『春に散る』では助演で出演する。
デビューして17年目。窪田は着実に年輪が刻まれ、いい顔つきをしている。これからも人間の持つ複雑さや強さや弱さを体現する俳優として歳を重ねてほしい。(安田佑子)
批評家コメント
吉岡里帆は「まっすぐ」のよく似合う女優だ。
かつては日本のハリウッドとも呼ばれた京都の太秦に生を受けた吉岡里帆は、高校3年の時、エキストラとして映画にかかわって以来、その魅力のとりことなる。
様々なアルバイトを掛け持ちしてお金を貯め、京都~東京を往復し、俳優養成所に通う日々を過ごす。その地道な努力が実を結び、高視聴率を誇ったNHK連続テレビ小説「あさが来た」の愛くるしいメガネっ娘の役でブレイク。
映画ヒロインとしてのデビュー作『明烏 あけがらす』では、抜群の反射神経でコメディエンヌとしての才能を発揮。昨年に公開され話題となった『ハケンアニメ』ではアニメ業界の覇権を争う新人監督に扮し、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞する等々、高い評価を受ける。
『島守の塔』ではボロ布のように砂浜に横たわる、吉岡里帆の顔のクローズアップから始まる。
場面は変わって、戦下の沖縄(昭和18年)。愛国心に燃える少女が、アメリカかぶれの妹に、日本国民としての心得を力強く説いている。沖縄の独特なイントネーションも巧みにあやつり、沖縄出身の池間夏海(吉岡にも劣らぬ名演技!)と絶妙なコンビネーションを見せてくれる。この時点では、色白で端正な顔立ちに若干の違和感を抱いたが、吉岡の全身を使った熱演によって次第にそれも薄れていく。
南国の砂漠で、累々とした日本兵の死体に囲まれ、アメリカ兵に銃を突き付けられながら、生と死の選択を迫られるクライマックスでは、思わず魂をわしづかみにされる。
書道八段。アルトサックスも吹く。写真集等ではセクシーな肢体を披露することもあり、演技派の女優としても、華のあるタレントとしても、さらに大輪の花を咲かせることは間違いなし。この先、どちらの道を選ぼうと、吉岡里帆らしく、どこまでもまっすぐに突き進んでもらいたい。(島敏光)
批評家コメント
アニメーション映画というのは不思議な存在だな、と思うことが常々ある。人気原作を持つ作品、テレビアニメで人気を博し特別版に近い形で上映されるもの、テレビアニメよりもハイクオリティな画質や音質で楽しめるもの。それぞれの魅力があるが、昨年9月に公開された『夏へのトンネル、さよならの出口』は、アニメーションでしか出来ない表現、映画館という集中力が高まる場所で観ることの意味が存分に発揮された作品であった。
第13回小学館ライトノベル大賞でガガガ賞と審査員特別賞をダブル受賞した八目迷の同名小説を映画化した本作。ポスターには制服姿の男女の姿が描かれ、タイトルにもある通り、夏の爽やかな青春ストーリーなのかと想像させられる。もちろんそういった側面もあり、10代の繊細な悩みや感情と成長が丁寧に表現されている。
しかし、本作で最も魅力的といえるのが、そのSF描写だ。WEBサイト等で読むことが出来る原作者・八目迷のインタビューでは、クリストファー・ノーラン監督の『インターステラー』の影響を大きく受けているという。主人公カオルとヒロインのあんずの出会いこそ、甘酸っぱい“ボーイ・ミーツ・ガール”ものに分類されるが、その後は目の肥えた映画ファンにもたまらないSF展開の連続となっている。
「願いが叶うけれど、100歳としをとってしまう」という都市伝説を持つ「ウラシマトンネル」。大切なものを失ってしまったカオルと、夢を叶えたい強い想いを持つあんずが、そのトンネルに入って目的を叶えようとするが…。物理学的な時間のミステリーと、傷ついた人々の心が癒えていく人間ドラマの融合が素晴らしく、田口智久監督のもと集結したスタッフによる作画や音楽の美しさも見事。鈴鹿央士(カオル)と飯豊まりえ(あんず)による声の演技もキャラクターにみずみずしさを与えている。映画でこそ味わうことの出来るアニメーションの魅力を存分に発揮している一本だ。(中村梢)
批評家コメント
今や日本の興行収入上位を占めるのは紛れもなくアニメーションだ。若者の多くがアニメーションを好む中、アートとしてスクリーン内を縦横無尽にキャラクターを動かす作家といえば、湯浅政明監督の名が上がるだろう。特に『夜は短し歩けよ乙女』では研ぎ澄まされた視覚による世界観で、恋する若者の感情をポップに描き出していた。
今作『犬王』では、松本大洋・キャラクター原案により設計された奇抜なルックと、独創的な和装で観る者を釘付けにする二人の主人公・犬王と友魚を、時に獣のように、時に儚く、時にアーティスティックに表現し、湯浅節を最大限に活かした手法でアートアニメーションとしてわれわれを歴史の世界へと誘った。しかも昨今囁かれるアニメと音楽の親和性を「平家物語」&「琵琶演奏」&「ロック」で奏でるという斬新極まりない発想は、明らかに世界レベルと言える。
特に注目したのは、古川日出男の原作「平家物語 犬王の巻」を現代にロックオペラとして制作する意味をしっかり捉えて構築されたストーリーラインだった。『エレファントマン』のように外見で人を判断する愚かさと共に、源平合戦で命を落とした平家の怨霊を琵琶の音色で鎮める供養を、ライブというスタイルで発想変換する。反戦と諸行無常の物語をイマジネーションの奔流とともに表現していた。
大友良英による観客を巻き込むかのような音楽の数々。そこに犬王の声を担当したアヴちゃん(女王蜂)による、映画館をライブ会場に変えてしまうかのような力強い歌唱がのる。更に野木亜紀子による、様々な登場人物の感情を終始うごめかせていた脚本。
それらの要素を見事にまとめあげ、犬王と友魚との出会いから、生き生きと輝きを放つ彼らから終始目を離せなくさせた湯浅監督の手腕。そして力強く独創的であり、一度、観てしまったら忘れられない画。それが『犬王』。これぞ自分たちの“表現方法”を信じた湯浅政明監督の素晴らしさであり、日本製作のアニメーションとして世界に誇れる作品だと確信した。(伊藤さとり)
批評家コメント
記録メディアという性質の強いドキュメンタリーとしては珍しく、しかもフォーカスが教育システムだというのに、じんわりとした温かさで胸に響いてくる。この映画が放つ不思議な力にまず驚かされた。
自分そのままで“いる”ことの幸せを、体いっぱいに表現している子どもたちの姿。彼らから伝わるのは、ありのままの自分を受け入れてもらえているという「自己肯定感」。この“圧倒的な”とでもいいたくなる自己肯定感には、誰もがはっとさせられるだろう。
この作品は主に公学校として、「体験学習」をカリキュラムの主軸に据えたある学園を追いかけたものだ。ここにはなんと、宿題もなければテストもない。先生さえいない。子どもたち自らが、生活そのものから題材をみつけ主体的に学びを深める。そばを育てるところから始まり、麺を打ち、食べてみる。彼らの学びはそばの風土歴史や数学などにどんどん広がっていく。子どもには無限の可能性があると、改めて実感させる彼らの学びの風景。
先進38か国の子どもを比較した、ユニセフのレポートがある。健康面でみると日本は第1位。しかし「精神的幸福度」は第37位。ワースト2位である。
かつて江戸末期に訪日した欧米人は、異口同音に「ここは子どもたちの楽園」と書き遺した。スクリーンには自由を“与えられた“子どもたちが、まるで楽園にいるかのようにのびやかに映っている。その姿は子供自立型の教育を行っていた寺子屋を描いた浮世絵とそっくりなのだ。
オルタナティブがどうのという問題ではない。また大きく時代が変わろうとしている、今、教育の主体とはなにかの問いは決して看過できない。これは教育の現場のみならず、全世代が共有すべきものだと痛感させられる。未来はいまの子どもたちが創っていくのだから。
映画には人や社会を変える力があると信じている。オオタヴィン監督の作品は、この『夢みる小学校』はもちろん、当たり前すぎて見過ごしていた価値観への気づきを提示してくれているようだ。小さな人間たちの、エシカルでおおらかな明るい未来のために。(日本映画批評家大賞機構事務局)
批評家コメント
2022年に上映された日本映画で、『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』ほど掘り出し物だった作品はない。昨年10月の公開から年をまたいでロングラン、熱烈なファンを作り出した。
中学2年のあるクラスに密着した竹林亮監督のデビュー作『14歳の栞』も2021年の公開後、SNSで広まり36都市まで上映は拡大され、今もスクリーンで再上映、再々上映を繰り返している。『14歳の栞』では主人公を作らず、クラス35人ひとりひとりの心の思いを丁寧にすくい上げたが、今作でも円井わん演じる吉川だけでなく、上司(マキタスポーツ)、5人の同僚、クライアント先、声のみの人物まで妙に全員が印象に残る。
青春ドキュメンタリーの前作と、オフィスが舞台のタイムループコメディである今作。話もジャンルも違うが、どちらも竹林監督が得意とする疾走感のある構成とあたたかい人間描写で長く愛される作品となった。
本作の企画の発端は、監督が所属し、今作の企画・製作・宣伝を一貫して担う会社の上司がタイムループのような同じツイートをしていたからだそうだ。それを監督と脚本家の夏生さえりを中心に12人が脚本を練り、怒涛の回数のタイムループで物語が破綻しないよう、頭脳明晰な社員を捕まえては一緒に気が遠くなる精査を重ねた。
実際の撮影現場では物語さながら、スタッフもキャストも「今、何周目の何曜日?!」と混乱することもしばしばだったというが、主演の円井は「監督の頭の中には完成形が見えているから」と信頼して演じたとインタビューで答えている。同じ演技の繰返しもあれば、間違い探しのように美術、衣装、行動が少しずつ変わるタイムループを一週間で撮り切ったというのも凄い。
20代の頃、竹林監督はCMディレクターとして働きながら、映画監督になる夢をあたためていた。映画界での彼の好発進は、映画人を夢見ながらタイムループにはまる者たちにも希望を与えるだろう。(安田佑子)
批評家コメント
ハリウッドでも議論となっている「(LGBTQ +、障がい者の役は)当事者が演じるべき」というテーマ。私見を述べるならば「そうであって欲しい」だが、そこには演技力が必要となる。本作の監督である飯塚花笑氏もトランスジェンダーであり当事者だが、インタビューの際に「日本ではまだまだ公表している俳優が少ない現状」と語っていた。
そんな監督がトランスジェンダー役に選んだ坂東龍汰は、“この役を演じなかったら一生後悔する”という思いで、トランスジェンダーの人々について撮影前から監督と一緒にとことん学んだそうだ。
ハードルの高い役を演じたから、今、必要なテーマの映画だから、賞に値するのかと尋ねられたら“そうではない”とは答えられない。しかし本作を初見で観た時のあの感覚は忘れられない。スクリーンの中にいるのは、俳優・坂東龍汰ではなく、明らかにひとりの女性に恋をした「真也」であり、肉体関係を持つことにも積極的になれず、子どもが好きなパートナーとの関係に悩むトランスジェンダーの「真也」だった。
物語の後半、二人で出した決断を松永拓野演じる俊平に相談するシーンがある。ここでの臨場感は、結(ユイ)役の片山友希との波長の合ったリズムから生み出され、三人の感情が大きなうねりとなって観客を“その場”に引き込むほどの見せ場となった。
よく俳優たちが「相手の演技をしっかり見て芝居を受ける」と言うが、これが上手い俳優は相手を輝かせつつ、映画全体を魅力的にする能力を持っている。本作では結の心の揺れが観客に共鳴しやすいのではと踏んだ飯塚監督により、真也は愛する人との未来を想像し、静かに葛藤するシーンの方が多い。そんな役の内面の感情が滲み出るように、坂東龍汰は「真也」を全身でもって体現していた。
思えば『弱虫ペダル』でも『スパイの妻』でも全く違う顔立ちだった。もしそれを“憑依型”と言うならば、そうかもしれない。間違いなく、毎回、彼は真っ白いキャンパスに役を緻密に描き上げている俳優なのだ。(伊藤さとり)
批評家コメント
片山慎三監督作品『さがす』で、伊東蒼はまたしても制服姿で走っていた。
短い登場シーンで強烈な印象を残した『空白』では威圧的な父親とうまく話せない娘の役で、スーパーで万引きを疑われ無我夢中に逃走していた。今作では父親の智(佐藤二朗)が万引きをしたと連絡が来たスーパーに、苛立ちを隠せない表情で走ってきて、関西弁で「ちょっとなにやってんの!」と父親を叱るしっかりした娘・楓を演じている。まるで正反対の役なのに伊東はそこに当たり前のように存在する。
周りの大人たちが失踪した智の捜索を諦める中、楓は強い意志で父親を探す。楓が、自分に空回りのケアをする教師の家に泊まった場面は印象的だ。教師の小さな子供がいちご味のゼリーを食べたいと両親にぐずる。そんな家族の会話に嫉妬し、こっそり自分のいちごゼリーをポケットに隠してしまう伊東のしらっとした顔がいい。
そして、父娘の関係のように永遠に続くと思われた智と楓の長い長い卓球ラリーの場面は、片山監督の伊東への絶対的信頼が感じられる。感情を爆発させることなくジョークも入れながら、ある選択について話す楓に胸がしめつけられた。今作の名シーンと言えよう。
芸歴が長い彼女が新人女優賞というのは少し違和感もあるが、伊東蒼という力のある女優をあらためて紹介したいと選ばせていただいた。
2011年、6歳でデビューし、『湯を沸かすほどの熱い愛』で新しい家族に心を溶かしていく小学生を演じた。この時すでに伊東の力は多くの人に知られたはずだ。現在高校3年生。学業と両立しながらの活動というが、近年の大舞台での活躍ぶりはどうだろう。NHK朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」、大河ドラマ「どうする家康」に出演、映画では『恋は光』でキーパーソン役を新たな姿で見せ、今春、紀里谷和明監督作品『世界の終わりから』では主演を務める。
今作で佐藤二朗に「怪物」と言わしめた伊東蒼が今後さらに、どんな素敵な怪物になっていくのか楽しみでしかたがない。(安田佑子)
批評家コメント
YouTuberとサラリーマンの異色の人間模様を描いた映画『神は見返りを求める』。『ヒメアノ〜ル』では戦慄の殺傷事件と物悲しい人間模様を、『空白』では息苦しさを覚えるほど迫真に迫ったサスペンスを、話題作を次々に生み出してきた吉田恵輔監督によるオリジナル作品だ。
再生回数が一向に伸びず悩んでいるYouTuberのゆりちゃんを岸井ゆきの、イベント会社に勤めるとにかく優しい田母神を演じるのはムロツヨシ。ある日合コンで知り合ったゆりちゃんの一生懸命さに気づかされた田母神は、撮影のための車を出したり、会社で着ぐるみをレンタルしてきたりと、無償で見返りを求めずに手伝いをするようになる。まさに“神”的な存在として、ゆりちゃんを支えていく。
とあることをきっかけに、ゆりちゃんは人気YouTuberとなり、田母神に冷たく接していく。恩を仇で返された田母神は、ゆりちゃんのプライバシーを同じくYouTubeで発信していくのだが…。ブームを超えて、一つのカルチャーとして定着しているYouTuberをモチーフに、吉田監督らしいシニカルさたっぷり描いていく本作。人気が出て天狗になるという、昔からある人間の悪癖に、“動画配信での暴露”という今ドキのエッセンスを加えた、非常にスリリングなストーリーだ。
これまで発表してきた全ての監督作品で脚本も担当している吉田恵輔。漫画原作ものも得意としているが半数はオリジナル作品となっており、その発想力の広さ、豊かさに驚かされる。仲良くなった2人の関係が崩れていく過程をこれでもかというほど嫌悪感たっぷりに、時に切なく描くのは吉田監督の得意とする所であるが、本作はYouTubeという身近な存在を描いているからこそ、ヒリつくほどにリアルだ。映画を観て笑い、怒りながら、こういう人っているよな、いや自分がそうなのかも…、とヒヤリとさせてくれる。「人間観察」という使い古された言葉では表現出来ないほどの観察眼に尊敬の念を抱く。今後はどの様な人間ドラマを描いてくれるのか、新作の発表が待ち遠しい。(中村梢)
※吉田恵輔の吉はつちよしが正式表記
批評家コメント
タイムループという王道の題材を、現代の日本社会に生きる人々が共感できる映画として成立させた『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』は、異例のヒットを記録した。しかも原作ものではないオリジナルストーリー。
発想の勝利ともいえるこの映画によって、たとえ規模が小さな日本映画であってもアイデアで勝負できるのだと可能性を広げてくれた
公開当時「最近、どんな面白い映画観た?」と聞かれると本作を挙げていたのだが、嬉しかったのは、普段洋画ばかり観ているような人にもこの映画の面白さが伝わっていたことだ。SNSでの口コミの力はたしかに大きい。しかしながらその現象は、“本当に面白い作品”にしか通用しない現象でもある。
小さな広告代理店で働く者たちが、同じ一週間を繰り返す。物語の舞台となるのは、オフィスのワンフロア。何十回と同じ一週間が繰り返される設定であるため、当然のことながら同じ空間で物語は展開し続ける。
タイムループしていることを強調するための同じ構図が必要となる一方で、一人また一人、タイムループに気づいていく。同じ画のなかで変化を出しながら単調にならないよう、俳優の芝居にも撮影方法にも工夫が求められただろう。
観客にとっても、さっき見た物語が繰り返されるが、同じなのにちょっとずつ変化があり、同じなのに次の展開にワクワクする。しかも「そういうことだったのか!」と、タイムループの種明かしをされて、すべて分かったうえで二度目の鑑賞をしたときに、つじつまが合っていなくてはならない
どれだけ素材があるかにもよるが、どちらにせよ編集はパズルのような作業だったはずで、それこそ編集中も同じ作業を繰り返しているような感覚だったのではないかと想像がつく。タイムループという外さない題材、面白い脚本、俳優の芝居力、それらをより面白いものに昇華させた編集のセンスを讃えたい。この映画の象徴ともいえる鳩の使い方は、最高に面白かった。(新谷里映)
批評家コメント
かつて豊島区南長崎にあった、さやかな木造アパート。ここに後の日本漫画の巨星である手塚治虫が入居したことから、「トキワ荘」という伝説が始まった。
手塚治虫という大きな背中を目指しながらトキワ荘に集ってきた若者たち。彼らは貧しさのなか互いに助け合い、それぞれのオリジナリティを求め漫画に向き合った。
トキワ荘から生まれた個性豊かな漫画家たちによる作品の数々は、世界をあっと驚かせもしたし、今なお色褪せず日本漫画文化の本流として脈々と受け継がれている。まさに小さな部屋から生まれた、大きな夢の結実である。
日本映画批評家大賞では、日本漫画の素晴らしさを称えるために、第20回からアニメーション関係の賞を設けている。この「ワタシタチのトキワ荘」とは、日本映画批評家大賞からアニメーション部門が独り歩きするために、新たに設置された社団法人。いわば兄弟姉妹のようなものである。
メタバースやサブカルチャーといった現代の世界観を巻き込みつつ、「トキワ荘」のスピリットを受け継ぎ、第二第三の手塚治虫を見出したい。トキワ荘が存在した豊島区から、独自の活動が始まる。
記念すべき初回の「ワタシタチのトキワ荘賞」をお受取りいただくのは、手塚治虫文化財団をおいて他にない。手塚治虫がいなければ、漫画家を夢みる若者たちがトキワ荘で出会うこともなかった。さらに言えば、日本の漫画やアニメの文化もまた違ったものになっていたのではないだろうか
手塚治虫文化財団といえば、特に印象的なエピソードが思い浮かぶ。あの「ジャングル大帝」と「ライオン・キング」の類似を巡っての騒動だ。自称ディズニー狂いというほど、ウォルト・ディズニーに憧れていた手塚治虫。この一件を本人が知ったらむしろ光栄に思うはずだ、と訴えることすらしなかった。
互いに刺激し支えあいながら、互いを尊重し、素晴らしい作品を生み出したいと願うスピリット。この手塚治虫マインドを礎に、次世代のクリエイターたちが生まれてくることを切に願っている。(日本映画批評家大賞機構事務局)
批評家コメント
座布団から広がる世界がある。落語家の口から繰り出される言葉だけで、観客の頭に噺の世界が像を結ぶ。それだけで落語という芸能のすごさが分かるものだが、立川志の輔の落語は、その話術は、われわれの脳裏に活き活きとした映像を浮かびあがらせる。これが映画的でなくてなんといえるか。
その立川志の輔の新作落語が、1本の映画となったのが『大河への道』である。中井貴一というひとりの映画人を“その気“にさせて、彼の企画から映画作品としてこの時代劇が生み落とされた。なんということだろう。
この映画『大河への道』という作品そのものも、もちろん良かった。映像となった時点でも落語の世界観を踏襲しつつ、そこにプラスして中井貴一はじめ制作陣のカラーも観えてくる。まさしく落語と映画が見事に結実した、稀有な作品なのではないだろうか。
もちろん落語が映画になるということ自体が珍しいことである。短編などの娯楽作品として部分的にはあるかもしれない。しかし落語自体が江戸時代をその舞台として映画化されたものは少ない。「居残り佐平次」を元にした、あの名高い『幕末太陽傳』くらいではないだろうか。
北陸富山に生を受け、「落語家になりたい」と28歳の時にカリスマといわれた立川談志に弟子入り。瞬く間に落語家としての才能を開花させた。談志師匠に「立川流の最高傑作」と評させたほどだ。
立川志の輔の落語は、まるで江戸時代の寄席のようだ。観客と一体となるように、話術で描き出していく江戸時代の景色と人情。本来であれば、落語には枕があって本編に入るのが通常だと思うのだが、志の輔の場合はそうはいかない。ズバッと本編に入っていく。志の輔落語のすごさ。そしてそれを受け止めついていく観客たちのすごさである。
今回の特別賞を立川志の輔という落語家に受け取っていただけることは、本当に嬉しいことである。日本人の心を捉えてきた時代劇。映画館に足を運ぶ人たちに時代劇をお届けすることの必要性を強く感じる昨今。本当に日本映画らしい作品が生まれたことを喜びたい。(日本映画批評家大賞事務局)
批評家コメント
岡田准一の役づくりは、驚くほど完璧である。なかでも近年、アクションを伴う作品においては、俳優としてだけでなく、殺陣やファイトコレオグラファー、格闘デザインとしてもクレジットされている。
しかしながら、アクション俳優という呼び方はそぐわない。というのは、岡田にとってのアクションは、演技の延長線上にあるものであり、役者にとって演技に繋がる武器となるものだと捉えているからだ。
岡田が役のために体を鍛え始めたのは18年前、映画『フライ,ダディ,フライ』まで遡る。その後TVドラマ「SP 警視庁警備部警護課第四係」をきっかけに、カリやジークンドー、修斗といった本格的な格闘技を身につけた。師範資格も取得し、続く『図書館戦争』『ザ・ファブル』シリーズでもその技術は活かされた。さらに時代劇では『蜩ノ記』で初めて本格的な殺陣に挑み、『関ヶ原』『散り椿』『燃えよ剣』と殺陣の腕を磨き続けてきた。
原田眞人監督との3度目のタッグとなった主演作『ヘルドッグス』では、格闘デザインを担当。自身の役だけでなく、メインキャラクターすべてのアクションを考案。単に格闘シーンとして見せるのではなく、アクションのなかにそのキャラクターの芝居が滲み出るのが、岡田の得意とするところだ。
エンターテインメントとしての魅せるアクションに、スタントマンの存在は欠かせないが、俳優自身がアクションもこなすことで、芝居に深みが増す、芝居が本物になることを岡田は証明した。そして岡田准一に続けと、ほかの俳優の目標にもなっている。
役のために技術を身につけ体型も変える──役に合わせて自身を変える役づくりが、デ・ニーロ・アプローチと言われてきたように、“岡田准一アプローチ”と言えるものを彼は作り上げたのではないか。そんな開拓者である彼を讃えたい、という経緯で特別主演男優賞に至る。
『ヘルドッグス』で岡田が演じた兼高昭吾、狂犬化した闇堕ち元警官というその役は、演技力と格闘技力、岡田准一の魅力を最大限に放射する役だった。(新谷里映)
批評家コメント
風吹ジュンという女優がずっと好きだった。最初にはっきりと認識した作品はNHKテレビドラマ「阿修羅のごとく」(79)での可愛らしい四女役で、その後、VHSビデオで見た映画『蘇る金狼』(79)は、当時、ティーンエイジャーだった私に大人の女性の魅力を教えてくれた作品だった。それは“小悪魔的な魅力”であり、同性をも惹き寄せる向日葵のような笑顔だった。
そんな風吹ジュンの代表的な映画のひとつが中原俊監督の『コキーユ 貝殻』(99)だ。中学時代からずっと思いを寄せていた男性に30年ぶりに再会し、少女のような表情を見せる大人の女性を演じ、報知映画賞主演女優賞を受賞した。その時の共演者、小林薫とは何度も共演し、石川慶監督の『Arc アーク』(21)では夫婦役で再共演を果たしている。
個人的な話をすると彼女とは何度か映画記者会見や舞台挨拶でご一緒しているが、阪本順治監督の『魂萌え!』(07)のキャンペーンでは私やスタッフにも愛用のプロポリスキャンディを配り、終始笑顔で場を和ませていたのを思い出すと、彼女が多くの現場に呼ばれる理由が見えてくる。そう、「人柄が顔に出る」とはまさに風吹ジュンのことであり、それが役のバックボーンを表現するのにも影響を与えるのだ。
今回の作品である工藤梨穂監督の『裸足で鳴らしてみせろ』では、風吹ジュンは主人公の青年のひとり、槙(諏訪珠理)と暮らす盲目の養母「美鳥」を演じた。ふらりと出かける時もお洒落を忘れず、つい面倒を見たくなる可愛らしさを兼ね備えた役。穏やかな人柄が分かる口調と愛を与える人だと観客に伝わる柔らかな表情で、青年達に行動を起こさせる。
物語は美しくも虚しく、どこまでも切なく、美鳥の願いである「世界旅行」を叶える為に、偽りの旅での音集めをする青年達の偽りの心を描いていく。
この映画のトーンである儚さの中心部分を彼女のあわい輝きを放つ演技が担い、若手俳優達が自由に感情を表現していたように見受けられる本作。その確固たる存在感と内側から醸し出されるしなやかな表現力は、「役者に賞味期限はない」という証そのものであり、これこそが風吹ジュンという女優が映画人に愛される理由だと確信している。(伊藤さとり)
批評家コメント
宮本信子は昨年公開された『メタモルフォーゼの縁側』でも、映画ファンの期待を決して裏切らない、安定した演技を披露してくれる。
この映画ではボーイズ・ラブ(BL)が重要なキーワードとなっているが、今どきのポップカルチャーをあつかうと、ともすれば浮ついた印象を与えることがあるが、ベテラン女優の存在が、それを地べたに引き戻す。
宮本信子は1945年に小樽に生まれ、名古屋で育つ。60年代から文学座等の劇団に学び、後にフリーとなる。舞台で鍛え上げられた着実な演技で、徐々に頭角を現し、映画でも60年代の『日本春歌考』、70年代の『男はつらいよ 純情篇』等で名バイプレイヤーとしての地位を確立する。
80年代に入り、『お葬式』『タンポポ』『マルサの女』等の伊丹十三監督による一連のヒット作品に主演。伊丹十三亡き後は、しばしのブランクを経て、『阪急電車 片道15分の奇跡』『キネマの神様』と一貫して良質な作品に出演を続け、数多くの賞に輝いている。
「あまちゃん」「ひよっこ」等、テレビでも目覚ましい活躍を見せている。シリアスよし、コメディーよし、ジャズや小唄もたしなむ。真正面から芝居に向き合いながらも、ジャズのレッスンに通い、「何歳になっても夢中になれるものあるということは大切なこと」と語る。何事にも真剣に取り組み、一歩一歩前進を続ける姿が、様々な媒体を通して、ひしひしと伝わって来る。
宮本信子の携わった作品からは常に良心の存在を感じる。それは少しずつ形を変えながらも、50余年の長きにわたって、自分自身の出演作を丁寧に選び続けて来た証。
『メタモルフォーゼの縁側』では、孫ほども年の離れた少女(芦田愛菜)とBL漫画を通して友情と信頼を築き上げていく孤独な老婦人の姿を、圧倒的な説得力を持って演じ切り、現代社会に孤立せず、難なく溶け込んで行くさわやか女性像を示してくれる。こんなステキな老婦人と陽の当たる縁側で、のんびりと語らうことが出来たら、どんなに楽しいことだろう。
宮本信子の進化はまだまだ終わらない。(島敏光)