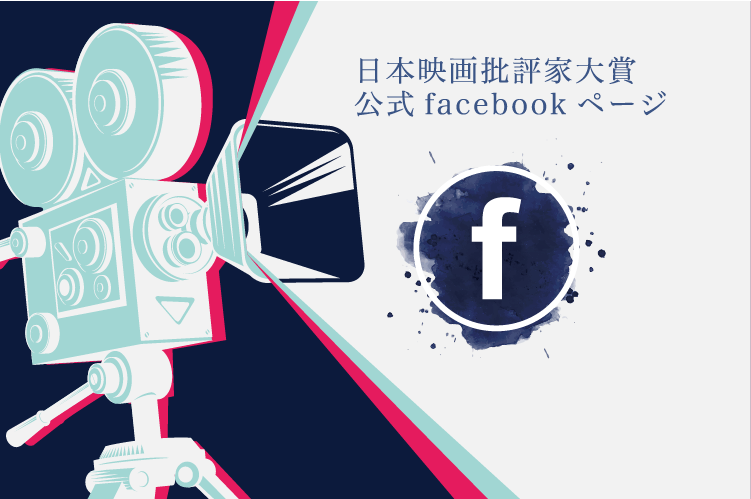新着情報
- イベント
『第31回日本映画批評家大賞授賞式』が開催されました

2022年5月30日(月) 有楽町の東京国際フォーラム(ホールC)にて、第31回日本映画批評家大賞の授賞式を開催いたしました。
国内の映画賞のトリを飾る日本映画批評家大賞。選考委員たちによって、厳正な審査のうえ選ばれた、2021年に際立つ活躍をみせた顔ぶれが授賞式にご登壇。
フレッシュな新人各賞から、技術賞、そしてベテラン俳優まで大変豪華なステージとなりました。
司会には自他ともに映画好きで知られる、笠井信輔アナと政井マヤアナがマイクをとっていただき、「映画人が映画人に贈る賞」というモットーにふさわしい、映画愛あふれるトークによって会場が満たされました。

第31回は、批評家が発する『ことばの力』をメインテーマに、各受賞者・受賞作品にふさわしい、『ことば』が選考委員によって各タイトルを表現しました。
受賞作品と受賞者はこちら
◎作品賞:『偶然と想像』(濱⼝⻯介監督)【会話劇へのあくなき挑戦】
◎主演男優賞:古⽥新太『空⽩』【怒れる男、古田新太の圧】
◎主演⼥優賞:瀧内公美『由宇⼦の天秤』【調和を乱しかきまぜる】
◎助演男優賞:鈴⽊亮平『燃えよ剣/孤狼の⾎ LEVEL2』【何色にも鮮やかに染まる】
◎助演⼥優賞:三浦透⼦『ドライブ・マイ・カー』【演技も名ドライバー】
◎監督賞:⼤友啓史監督 『るろうに剣⼼ 最終章 THE FINAL』『るろうに剣⼼ 最終章 THE BEGINNNG』【新時代の挑戦者】
◎ドキュメンタリー賞:『くじらびと』(⽯川梵監督)【大画面でも溢れ出る生命のエネルギー】
◎アニメーション作品賞:『フラ・フラダンス』(⽔島精⼆総監督/綿⽥慎也監督)【真っ直ぐな共感】
◎アニメーション監督賞:庵野秀明監督『シン・エヴァンゲリオン劇場版』【想像を超えていく創造】
◎新⼈監督賞:穐⼭茉由監督『シノノメ⾊の週末』【“今”の女性像を追い続けてほしい才】
◎新⼈監督賞:阪元裕吾監督『ベイビーわるきゅーれ』【アップデートされた価値観とアクション】
◎新⼈監督賞:藤元明緒監督『海辺の彼⼥たち』【巧みな問題点の伝え方】
◎新⼈男優賞:佐藤緋美『ムーンライト・シャドウ』【感覚をカタチにする才能】
◎新⼈男優賞:Fukase『キャラクター』【才能と努力が生み出す脅威】
◎新⼈⼥優賞:伊澤彩織『ベイビーわるきゅーれ』【裏の顔を持つ映画人】
◎新⼈⼥優賞:⽯川瑠華『猿楽町で会いましょう』【ありきたりの特別】
◎新⼈⼥優賞:伊藤万理華『サマーフィルムにのって』【多才な感情表現】
◎新⼈⼥優賞:⻄川洋⼦『いとみち』【自分の言葉を持つ新人女優】
◎脚本賞:⻄川美和『すばらしき世界』【稀代のストーリーテラー】
◎編集賞:堀貴秀『JUNK HEAD』【映像の錬金術師誕生】
◎撮影賞:上⽥義彦『椿の庭』【うつろう美しさの記録】
◎特別賞:⼩倉智昭【ラジオの力】
◎ゴールデン・グローリー賞:荒⽊⼀郎【とんがり続ける極上の才能】
◎ダイヤモンド⼤賞:富司純⼦『椿の庭』【併せ持つ静と動の美しさ】
批評家コメント
2021年を彩る濱口竜介監督の『偶然と想像』は、日常の偶然をテーマに3つの物語を映像化した作品だが、そこには「映画」そのものの構造を新しい視点で直視する、大胆かつ繊細な試みが秘められている。そして、濱口監督の映画理念とその試みが作品を通して見事に合致したとき、この映画は、最も作品賞に価する風格をたたえることとなる。
この監督の熱い映画に対する思いと、勇気あるその挑戦者としての姿勢が、各国際映画祭での輝かしい評価へと繋がり、かつ世界の映画人に刺激と共感を与えたものと思う。
濱口監督の映画への挑戦を2点たどることができる。そのひとつは、オムニバス形式の開拓。かつての映画界では、この形式は興行的に敬遠されたジャンルである。その理由は、短編映画集では物足りなさが先行し、観客側にも映画で満腹感を得られるのは長編であるという通念があったからだ。また、製作側からするとこの形式は、話数分の独立した映画の制作に等しくコスト高となると考え、合理的ではないとみなされていた。
が、今回の濱口作品は、〝偶然〟というブリッジを巧みに活用し、この形式のもつ短所を長所に置き換え、全体を通して観応えのある1本の作品に仕上げている。蛇足だがオムニバスの3話とも同時代の設定にし、話を凝縮させることにより制作費も想定内としたようだ。
もうひとつの挑戦は、“シナリオにおける偶然性”を逆手に取っているところ。
本来、シナリオ作法上での偶然性の処理は、それなりの伏線が張られ、ご都合主義にならないように構成することが要求される。ところが濱口監督は、このタブーをも難なく覆し、人生もまた説明し難い偶然の機微によって営まれていることを証明してみせる。
濱口監督の挑戦は、かつてのフランスのヌーベルバーグ派を彷彿とさせる理念と技術に裏打ちされているとともに、これからの日本映画での新しい表現の形をあざやかに提示してくれた。(川村蘭太)
批評家コメント
『ヒメアノ~ル』、『愛しのアイリーン』、『BLUE/ブルー』など衝撃とともにその才能を見せつけた吉田恵輔監督が2021年に発表した映画『空白』。オリジナル脚本で書かれた本作は娘の事故死の真相を探るモンスター化した父親と、その父親に翻弄される青年と周りの人物たちの姿を描いたヒューマンサスペンスだ。
映画公式サイトのコピーに「迫り来る古田新太の狂気、逃げられない松坂桃李」とあるとおり、主演・古田新太の狂気が凄まじい。
普段から娘に対して高圧的で、観客からすると決して“良い父親”では無い、主人公の添田充(古田新太)。娘の花音はスーパーで万引しようとしたところを店長の青柳直人(松坂桃李)に見つかり、逃げているうちに車に轢かれて命を落としてしまう。添田は花音の無実をはらすべく、「本当は万引きをしていなかったのではないか」「青柳の勘違いで事故死したのではないか」と、青柳を執拗に責めたてていく。
怒鳴る、わめくは当たり前。青柳の食事や住まいにまでつきまとい、嫌がらせをエスカレートしていく添田。漁師仲間や部下、元妻にも暴言で当たり散らしていく。娘を亡くすという悲劇に見舞われた父親ではあるが、その振る舞いの恐ろしさから、「被害者・加害者とは一体何なのか?悲しみと怒りの先には何が残るのか?」と考えさせられる2時間弱であった。
古田といえば、数々のドラマ、映画、舞台で活躍する日本を代表する名優であり、役柄もコミカルなものからシリアスなものまで幅広く、バラエティー番組でも多くの視聴者に愛されている。そんな古田が演じる“モンスター親父”というだけで、鑑賞前から期待は高まっていたが、その想像もはるかに超える怪演ぶり。さらに恐ろしいだけではなく、寂しさ、悲しさをふとした表情で伝えてくる凄さ。
古田新太でなければこの映画は決して完成しなかった、そう思わせてくれる堂々たる主演であった。 (中村梢)
批評家コメント
一昨年の『新聞記者』が高い評価を受けたことでもわかるように、これまで目を背けることが吉とされてきたゆがんだ社会の問題は、ひとごとではなく自分ごととしてとらえられるように。そういう作品に光が当たるようになったことによって求められるのは、高い知識、教養、そしてそれを芝居に落とし込んでいく能力。昨年、それを実現してくれたのは間違いなく春本雄二郎監督の『由宇子の天秤』であり、主演を務めた瀧内公美の力であるといえるだろう。
瀧内が演じたのは主人公、ドキュメンタリー監督の木下由宇子。父が経営する学習塾を手伝いながら、3年前に起きた高校生自殺事件のドキュメンタリー番組の制作をしている。
その事件は、いくつかの原因が取り沙汰されたことで報道合戦となり、結果としては自殺者を増やしてしまった。その事件を再検証する由宇子は、ひょんなことから父の学習塾での不祥事を知ることになり、加害者側の視点を得る。報道と取材のあり方、マスメディアの持つ力の功罪に切り込んだ意欲作だ。
由宇子を演じた瀧内公美の芝居が素晴らしかったのは言わずもがな。これまでも社会派作品できらりと光る存在を放っていた彼女が、そのジャンルにおける代表作を得た、ともいえる。
だが、特筆したいのは、彼女がこの作品に出るきっかけだ。彼女は、春本監督の長編デビュー作『かぞくへ』を劇場で観て、その場にいた監督に直談判で次回作へのオファーをお願いしたという。この意欲には素直に驚かされた。役者がマネジメント事務所に守られることで、彼らのパブリックイメージは保たれるものの、役者側からすると作品で実力を伸ばすことがなかなか難しい。マネジメント側が強大な力を持つ日本の芸能界の難点でもある。そのパワーは昔ほど強くなくなったといわれているものの、他国のように役者本人が自由に作品を選んで芝居するという土壌には、まだまだ道のりは遠い。
そんな状況を考えると、瀧内公美のような行動力、そしてこのような難しい役に自ら飛び込んでいく意欲には感動するほかない。
(よしひろまさみち)
批評家コメント
『HK 変態仮面』、『俺物語!!』、大河ドラマ「西郷どん」などなど、役にあわせて肉体改造をし、見た目の激変で驚かされることが多い鈴木亮平。激変ばかりが取り沙汰されてしまい、肝心の芝居が霞んでしまう報じられ方をされるのは、彼のキャリア初期から観続けている者としては非常につらかった。
昨年の出演作『燃えよ剣』の近藤勇役、『孤狼の血 LEVEL2』の上林成浩役も、その見た目の違いが大きく報じられ、「そうじゃない」と筆者は思ってしまった。立派な体躯とモデルもこなした端麗な容姿を持って、真面目に芝居に取り組む役者ほど、イメージの変化を敏感にとらえられてしまう。違う、そうじゃない。見た目を変えるのは役者の責務であり、役にどれだけ真剣に向き合っているか、のバロメーターでしかない。問題は芝居のクオリティなのだ。
そういった周囲の雑音を気にせずに、質の高い芝居をサラリとやってのけている役者の一人が鈴木亮平だ、と昨年の2作で確信した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、1年以上の公開延期を余儀なくされた『燃えよ剣』での近藤勇役は、新選組の実質的リーダー土方歳三の上長としての威厳と風格を備えた存在感を放つ。幾度となく映像化されてきた題材だけに、ともすれば比較されてしまう役どころだが、30代後半を迎えた彼にしかできない緩急バランスの見事な芝居で、他のキャストを下支えする度量を見せた。
『孤狼の血 LEVEL2』では、規律のある任侠の世界で、自分こそがルールという狂気を携えた絶対悪・上林を熱演。ヤクザ映画というジャンルを復活させることに成功した前作を受けて、どんな悪役を見せてくれるのか楽しみにしていたが、想像をはるかに超えた極悪っぷり。脚本以上の絶対悪の存在感で、他の登場キャラクターを圧倒するほどだった。どちらも助演の意味を解して、作品のクオリティをグンと上げることに成功しているといえるだろう。
今の鈴木亮平にしかできない見事な芝居。これから見せてくれる芝居も楽しみで仕方ない。 (よしひろまさみち)
批評家コメント
「赤いサーブ900を見事に運転してくれた三浦透子さん…、獲りました!」と濱口竜介監督は第94回米アカデミー賞国際長編映画賞受賞スピーチの最後に三浦への感謝を述べた。運転免許を持っていなかった三浦透子を、「乗っているのを忘れるほど運転が上手いドライバー」瀬崎みさき役にオファーした濱口監督の目に狂いはなかった。
『ドライブ・マイ・カー』は村上春樹原作の3つの短編小説とチェーホフ、そして濱口監督のオリジナル要素を編み上げた人間ドラマである。演出家で俳優の家福(西島秀俊)は妻を失い、喪失感を心に封じ込めたまま演劇祭の仕事で広島へ。主催者の規定からドライバーを雇わねばならず、家福の愛車を運転することになるのがみさきだ。
みさきは母親との愛憎の末、頬と心に傷がある。表情を遠い過去に置いてきたかのような三浦の顔がいい。車の移動シーンでは、みさきが映っているシーンでも映ってないシーンでも、家福の物語を遮らない温度でそこにみさきの存在を感じる。「彼女にはどんな物語があるのか」と気になり始めてからは、タバコを頻繁に吸う仕草や、フレームから消えたと思ったら犬が好きなことがわかる一瞬など、彼女の一挙手一投足から目が離せなかった。
みさきは家福の凍りついた悲しみを溶かすキーパーソンで、自身も家福との出会いで閉じ込めていた言葉を語り始める。恋愛でも友情でもない、心通い合う他人の男女の絶妙な距離感を静かな存在感で演じた三浦の貢献度は大きい。
彼女は今作で第95回キネマ旬報ベスト・テン、第64回ブルーリボン賞で助演女優賞、第45回日本アカデミー賞では新人俳優賞を受賞している。
6歳でCMデビューし、俳優、歌手、ナレーターとしても活躍する26歳。主演助演含め出演映画は25本を超え、演じる役は幅広い。今作を経た三浦は『スパゲティーコード・ラブ』ほか、NHKの朝ドラ、大河ドラマへの出演を果たした。特に大河へは今作を見た脚本の三谷幸喜が三浦を起用したという。作品の空気を捉え、相手に寄り添う演技が得意な三浦が、助演、主演のどちらでもますます輝く俳優になると信じている。(安田佑子)
批評家コメント
大友啓史監督は挑戦者だ。既存の枠にとらわれずに、私たちが映画というエンターテインメントに求めているものを、先取りするかのように捉え形にしてきた。NHKという組織から羽ばたき独立してから10年。「次は一体どんなものを見せてくれるのか」と期待せずにはいられない作品を作り続けている。
なかでも『るろうに剣心』シリーズはやはり特別だろう。漫画原作の実写映画化は、これまでも現在も決して珍しいものではなく、むしろ溢れている。ところが、シリーズ1作目の『るろうに剣心』を観たときに驚かされたのは、原作の世界観を壊すことなく、私たちが生きる世界とどこか地続きであるかのようなリアリティと、緋村剣心役の佐藤健をはじめとする俳優たち自ら立ち回るアクションに魅せられた。「何だ、このアクションのクオリティーは!」と、衝撃と感動に打ち震えたのを強烈に覚えている。日本映画のアクションエンターテインメントの可能性を大きく広げた瞬間に立ち合った気がした。
このシリーズは、計5作品からなる。今回の監督賞は、名目上『最終章 THE FINAL』『最終章 THE BEGINNING』としての賞になっているが、同じ俳優と同じスタッフで、10年で5作のシリーズを撮り、しかも毎回前作を上回る挑戦を仕掛けてきた、シリーズ全体に向けた賞でもある。
技術的なことを挙げればきりが無いが、シリーズを締めくくる「最終章」での最大の挑戦は、終わりと始まりを同時に描いたことではないか。これまでずっと謎に包まれていた主人公の頬の傷の理由が『THE FINAL』で明らかになり、『THE BEGINNING』では流浪人・緋村剣心が生まれる出来事が描かれる。そして、『THE BEGINNING』は1作目の『るろうに剣心』に繋がっていく。まるで無限ループのように。
また、日本の実写映画は海外へのアプローチが苦手とされるなかで、海外での『るろうに剣心』の認知度はとても高い。日本だけでなく、国境を越えたエンターテインメントとして『るろうに剣心』シリーズを世界に放ってくれたことも、日本映画の底上げになったはずだ。(新谷里映)
批評家コメント
SGDsという言葉自体が消費されているかのような現代に、人と人とが社会を形成し、そして自然という大きな全体と「共生」している、あるプリミティブな村の営みをこのドキュメンタリーは真っ向からとらえる。
生きること、それは当たり前のことだが、他者の命を自らの体に取り入れることである。『くじらびと』は生々しいほどに勇ましく、そして悲しいほどに美しくその“生“の承継を描き出す。
人口1,500人のインドネシアの小さな村・ラマレラ。その村では何と、体長15メートルを超えるマッコウクジラにモリ一本で跳びかかるという、驚くべき鯨漁が今でもおこなわれている。時には死者も出る、文字通り命がけの壮絶な漁。しかし1頭のクジラが獲れれば村の全員が2か月生きられる。なんと雄大でおおらかな共生の営みだろう。
本作はその漁の様子をドローンや水中カメラなどを駆使し、臨場感あふれる映像によって描いていく。ものすごい圧巻の映像美であり、他に類をみないドキュメンタリーの現場だ。
足掛け30年という歳月をかけ、石川監督はこのラマレラ村の祈りと感謝のなかで行われる鯨漁を追いかけてきた。監督の写真集や本作からは、生命のつながり、人と人のつながり、自然という全体とのつながり、そして生きることの本質とは何かをストレートに問いかけられる。
特に本作では、その勇壮でダイナミックな映像の中に、あらがえぬ“生“という宿命を背負った“生きる者たち”の悲しみが見え隠れする。グローバル資本にどっぷりと浸かる私たちに強烈に突きつけてくる、まさに「生命の現実」である。
本作からはまたドキュメンタリー作品の神髄というものを強烈に感じた。ナレーションや説明はほとんど入らない。雄弁かつ美しい映像と、そして“今そこに生きる“生身の人間の言葉で紡がれた『くじらびと』。作家の存在を極限まで排しつつ、逆説的に作品の核へと観客を導いていく。スクリーンには石川監督が伝えたかったであろう、生の本質が結晶となってきらきらと輝いてみえた。
(日本映画批評家大賞機構事務局)
批評家コメント
とても気持ちのいい映画だ。そして誰もが共感するとても深いメッセージが込められている映画でもある。
フラダンスの映画と言えば、真っ先に実写映画『フラガール』を思い浮かべる人が多いだろう。このアニメーション『フラ・フラダンス』も『フラガール』と同じく、スパリゾートハワイアンズが舞台であるが、大きく異なるのは、『フラガール』は常磐ハワイアンセンター(当時の名称)ができるまでの物語であるのに対し、『フラ・フラダンス』は現在のスパリゾートハワイアンズで働き始める若者たちの物語であることだ。
地場産業として地方を舞台にしていること、フラガールという“仕事”に焦点を当てることで、若者だけではない、幅広い年齢層に響く内容になっている。しかも、このアニメーションのそもそもの成り立ちは、東日本大震災で特に大きな被害を受けた岩手県・宮城県・福島県、それぞれを舞台にしたアニメーションを制作する「ずっとおうえん。プロジェクト2011+10…」の一貫でもある。
「乗り越えられる」─これはフラガールを目指す社会人1年生の主人公・夏凪日羽を陰ながら見守る鈴懸涼太というキャラクターのセリフだ。フラガールたちの成長を描くと同時に、震災という未曾有の出来事を取り入れ、乗り越えられる、乗り越えて来たんだと、観る者それぞれが自分ごととして受け止められるように作られている。
また、スパリゾートハワイアンズの再現率はとても高く、2年以上にわたる同施設の取材協力を得て制作、震災によって出来てしまった建物のズレも再現している点からも制作者たちの想いが伝わってくる。
見どころとなるダンスシーンでは、フラダンス特有の動きがとても滑らかに描かれている。現役ダンサーが踊る動きをモーションキャプチャで撮り3Dで描く手法を取ることで、アニメーションのなかにリアリティが生まれる。リアリティが生まれることで、共感も生まれる。頑張ること、乗り越えることを、こんなにも真っ直ぐに描ききったことを評したい。(新谷里映)
批評家コメント
2021年のアニメーション界最大のトピックスといえば、「エヴァンゲリオンが完結したこと」と言っても過言では無いだろう。
1995~96年に放送されて社会現象的なブームとなったテレビシリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」。コミック化、映画化、グッズ化など様々なメディアミックスを行いながら、影響を与え続ける、世界的なコンテンツの一つである。
「新世紀エヴァンゲリオン」の原作者である庵野秀明監督は、芸術大学在学中に自主製作映画グループへの参加から、アルバイトとして『超時空要塞マクロス』や『風の谷のナウシカ』の原画、アニメーション制作へも加わり、宮崎駿監督らの評価を受けていく。その後、『トップをねらえ!』『ふしぎの海のナディア』で監督、演出方面として才能を発揮していき、1995年に「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズがスタート。アニメファンのみならず、日本中、世界中にその名を知らしめた。
実写映画も積極的に監督し、2016年公開の『シン・ゴジラ』は多くの映画賞に輝いている。監督自身が“特撮ファン”であることが十二分に発揮された、ゴジラへの愛にあふれ、クセものぞろいの人間関係が魅力的な『シン・ゴジラ』だが、「新世紀エヴァンゲリオン」も庵野監督の愛、好きなもの、興味関心が溢れ出している作品なのではないかと思う。
2021年3月8日、「エヴァンゲリオン」が完結した。27年もの長い期間培ってきた、設定の格好良さ、恐ろしさ、悲しさ、楽しさ、全てをそのままに、さらに新しい解釈が加わった形で突き進んでいく155分。難解な言葉も多く「理解出来ない」部分ばかりで頭は混乱しているのに、楽しい。「エヴァンゲリオン」の原作者であり、監督、脚本を務める庵野監督の唯一無二の才と発想力を改めて感じさせてもらった時間であった。
これだけ世界中を熱狂させた作品でありながら、最後は庵野監督の地元に回帰するという演出にも驚かされた。戦闘シーンの描き方の格好良さ、エポックメイキングな音楽の使い方など素晴らしい点は書ききれないほどあるのだが、多くの観客が「これは自分のための物語」と思えたことが「新世紀エヴァンゲリオン」の大きな力なのではないかと思う。作品自体は終結をむかえたが、まだまだ、この先何年も何十年もエヴァンゲリオンを味わって楽しんでいきたい。庵野秀明監督、本当にお疲れ様でした。(中村梢)
批評家コメント
穐山茉由監督は、じつはこの作品よりもずっと以前、映画美学校の修了制作作品である『ギャルソンヌ-2つの性を持つ女-』のときに「この人は近い将来、大きく成長する」と確信していた。その30分強の短編は第27回レインボー・リール東京(東京国際レズビアン&ゲイ映画祭)のコンペティション部門であるレインボー・リール・コンペティション 2018に出品。性的マイノリティのなかでも、なかなか理解と認知が進んでいないインターセクシュアルの女性を主人公にした本作で、LGBTQコミュニティにも受け入れられる出来栄えを見せた。コミュニティの人でもなかなか難しいテーマ設定を軽やかにこなしたことに感嘆したのを忘れられない。
そのとき穐山監督にうかがって印象に残ったのは、監督は映画制作専業ではなくファッションブランドのPRとして活躍していたこと。おしゃれに興味がある女性ならばたいがいの人が知っているブランドで働きながら、自分がやりたい映画制作を併行して行っていることを知って驚くとともに、今の日本映画界の問題を感じた。
今やスマホを使って長編映画が撮れて、動画配信ができる時代。商業映画とは桁違いにコストを抑えたインディペンデント映画が注目を浴びることもしばしばある。それはすなわち、誰もが映画監督になるチャンスを持っているということ。だがそのいっぽう、商業映画を量産する大手映画会社のシステムは昔と違い、現場で若手を育てる余力がなくなった。だからこそ、映画制作を目指す若者は、自発的に映画を学び、それが生業となるまでは、別のやりたいことを並行して切磋琢磨する。なにかと厳しい社会だが、やりたいことを追求することイコール愚直にそれだけをやり続ける時代は終わったのだ。
『シノノメ色の週末』はまさにその世代の生き方を描いた秀作。今を生きる等身大の20代女性を主人公に、監督自身の生き方をなぞったような物語。ここから監督の将来性と映画界を目指す若い世代の青写真が見える。 (よしひろまさみち)
批評家コメント
2021年も様々な映画がSNSで話題となったが、この『ベイビーわるきゅーれ』も、SNSで観客の熱いコメントがあふれ、大きな盛り上がりを見せた一作だ。同年7月に公開されると、 上映館が続々と増加し、 池袋シネマロサでは2022年2月まで上映が続き、インディーズ映画として異例のロングランヒットを記録。各映画レビューサイトでも高いスコアを記録している。
本作を手がけた阪元裕吾監督は現在26歳の若き奇才。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)在学中に制作した『べー。』 で「残酷学生映画祭2016」のグランプリを受賞。「ゆうばり国際映画祭」等で発表された、『ぱん。』『スロータージャップ』など、残虐で理不尽なのにどこかシュールな作風が特徴的だった。
その後、2021年に公開された『ある用務員』にて、その本格的なアクション展開に驚かされた。福士誠治の初主演作である同作は、女子高生のボディガードながらも学校の用務員として潜んでいる男を描いたクライムアクションなのであるが、この作品に出ている女子高生2人組を演じている髙石あかりと伊澤彩織が、同じ様な設定で主人公になっているのが『ベイビーわるきゅーれ』なのである。
女子高生と殺し屋という2つの顔を持つ、ちさと(髙石)とまひろ(伊澤)だが、生活能力が低く社会に適合できていない。そんな2人が高校卒業後の生き方を見出していくのであるが、このポンコツ2人の日常描写とアクションシーンとの対比が非常に爽快なのである。スタントマンとして活躍している伊澤の超絶アクション、ダンス&ボーカルユニットの経験を持つ髙石によるキュートな魅力、園村健介によるアクション指導も見事なのだが、キャスト&スタッフの魅力をまとめあげた阪元監督の手腕が素晴らしい。
何より、「戦い以外を知らない殺し屋女子高生が社会に出たら」という設定のオリジナリティがさすが。同じく2021年に公開された『黄龍の村』の設定にも驚かされたが、今後、阪元監督の脳内から驚く様な映画が誕生してくれることが楽しみで仕方がない。
(中村梢)
批評家コメント
良い映画には、その時代の、その国の社会が描かれている。藤元明緒監督が送り出す映画には、日本社会と日本と関わりのある国の社会、その両方が描かれている。
長編初監督作品『僕の帰る場所』は、日本に住むミャンマー人家族の物語だった。日本で育った母国語が話せない子供たちとミャンマーへの想いが募る彼らの母親、そして離れ離れになってしまう父親との交流から、家族の在り方を問い、生きる場所を見出していく、温かくも逞しい物語だった。
長編2作目『海辺の彼女たち』の主人公は、技能実習生として日本で働く若いベトナム人女性たちだ。故郷の家族のために出稼ぎに来ていているが、不当な扱いを受けて職場を逃げ出した彼女たちは、不法滞在者となり、生きていくために北国の漁港にたどり着く。彼女たちの目線を通して、日本で暮らす外国人労働者の実態を映し出していく。
1作目も2作目も、どちらにも共通するのは、社会が抱える問題を組み込んだオリジナル脚本であること。日本と、日本と繋がりのある国と、その狭間で力強く生きようとする人々の暮らしを描いている。ニュースでは伝えきれない社会の片隅に生きる人たちに焦点を当てている。見方によってはドキュメンタリーのような感覚を覚えるシーンもあるが、それは藤元監督の入念なリサーチゆえの表現方法だ。知らない日本、知らない世界、でも自分にとっても身近な問題であることに心を動かされる。
藤元監督の作品には、誰もが知っている俳優は登場しない、小説や漫画の映画化でもない、ニュースに取り上げられる可能性も低い題材かもしれない。けれどそこには、友情があり、愛があり、人生がある、とてもドラマに満ちている。
きっとこれからも藤元監督は、多くの人が見過ごしがちなものを掬い取り、映画として伝えてくれることだろう。日常にこそドラマがある、そのドラマにこそ人生において大切なものがある、彼の作品には気づかされることばかりだ。(新谷里映)
批評家コメント
その俳優の演技力を語るとき、技術的な巧さもあれば、存在感から醸し出される感覚的なものもあって、演技とは一体何なのかと考えさせられることがある。
『ムーンライト・シャドウ』で柊という青年を演じた佐藤緋美のキャリアはまだ始まったばかり。2018年に舞台「書を捨てよ町へ出よう」で主演に抜擢され俳優デビューを飾り、映画は3本目になるが、柊役の佐藤緋美から感じたのは、先に挙げた演技で言うならば、確実に後者だ。
彼が演じた柊は、小松菜奈の演じる主人公のさつきと同じくらい、難しい役ではないかと思うのだ。さつきと柊は、それぞれ恋人を事故で亡くす。そして、それぞれ喪失感と向き合いながら立ち直る姿が描かれるが、立ち直っていくアプローチは、実は対照的だ。さつきが肉体的な表現だとすると、対になる柊は精神的な表現、よりファンタジックさを内包している。
そのファンタジックさと佐藤緋美がもともと持っている存在感が、みごとに重なり合ったのが柊役だった。柊役はオーディションで決まったそうだが、監督のエドモンド・ヨウは、佐藤緋美を「とても映画的」だと表現している。やはり感覚的な何かを持っている俳優なのだろう。
映画的、感覚的、存在感、という言葉はどれも抽象的で曖昧ではあるが、セーラー服姿の柊が違和感なくスクリーンのなかに居ることが、その理由付けになっているのではないだろうか。亡くなった恋人の服を着て過ごす、一般的には女性の制服とされるものを纏っているのに、まるでその行為が彼にとっては当たり前の儀式か何かのように説得力を持たせているのは、佐藤緋美の才能に他ならない。
柊が、現実と幻想の狭間にいるような時間が描かれるシーンがある。セーラー服を洗うドラム式洗濯機の前で佇むシーンだ。あの時の表情に引き込まれた。哀しみと喪失と艶やかさが混ざり合うような、何とも魅力的な表情に、引き込まれた。すごい俳優がやってきた、とゾクッとした瞬間だった。 (新谷里映)
批評家コメント
俳優・Fukaseが誕生した。
永井聡監督作品『キャラクター』でFukaseが演じた殺人鬼、両角(もろずみ)は挙動不審で天真爛漫だ。首や手の動きの怪しさが両角の持つ闇の深さを想像させる。Fukaseからミステリアスで少年のようにピュアな雰囲気は以前から感じていたが、何より今作で恐ろしさを覚えたのは声だ。Fukaseは声の表現を長年追求してきた人だ。声の強弱や高低だけではなく、温度や深さでセリフを放つ。歌で聴き馴染んだ透き通る声が、こうも怖く聞こえるものかと驚く。
漫画家を志す山城(菅田将暉)はお人好しな性格から悪人が描けなかったが、殺人現場とその犯人・両角を目撃した経験が彼をベストセラー作家に。山城の描く殺人鬼は自分がモデルに違いないと確信した両角は、漫画のストーリーどおりに殺しを繰り返す。漫画とリアルを交差させながらドラマティックに展開する今作は、長崎尚志が書き上げた完全オリジナル脚本。原作漫画もアニメもない、ヴィジュアルイメージもまっさらな両角役に白羽の矢が立ったのが、日本を代表するバンドのひとつ「SEKAI NO OWARI」のFukaseだ。
演技が初めてだったFukaseがこの役のために1年半、レッスンを受けたと聞き、表現者としてのプロ意識を感じた。役に向き合える時間を長くもらえることは幸せでもあるのだろうが、殺人鬼を理解する期間としてはこの上なく辛い時間だったのではないか。山城に両角はアイデンティティーを与えられたと思い、両角は山城に栄光と絶望を与える。理由のある狂気をFukaseは真摯に表現し、作品に両角というキャラクターの強い印象を残した。今作でFukaseは第46回報知映画賞、第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞している。
福山雅治、星野源、野田洋次郎、今作のもう一人の主演・菅田将暉、海外ならレディ・ガガなど、ミュージシャンでもあり俳優でもあるアーティストは多くいる。本業がどちら、という時代ではない。本賞が今後の演技の可能性を追求する彼のモチベーションとなったなら嬉しい。(安田佑子)
批評家コメント
伊澤彩織をスクリーンで初めて見る人であれば、アクションシーンに入ったその瞬間、「こいつ、ただものじゃない」と思うだろう。伊澤は『キングダム』、『るろうに剣心 最終章 THE FINAL/ THE BEGINNING』、『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』などでスタントダブルを務めてきたスタントパフォーマーでもあるのだ。
高校を卒業したての殺し屋、伊澤演じる「まひろ」と「ちさと」(髙石あかり)。組織の命令で「オモテの顔」の修行をすることに。まずは共同生活、そして、殺しの報酬で生活には困っていないのだが、社会勉強の一環としてコンビニや飲食のアルバイトに挑むも、仕事ぶりや人間関係は完全に社会人失格。殺し屋女子ふたりのゆるゆるの私生活と、園村健介がアクション監督を務める激闘ファイトシーンとのギャップが楽しい作品だ。
芸能事務所の養成学校時代、映画に「アクション部」があることを知り、本格的にアクショントレーニングを始めた。今作のメガホンをとった阪元裕吾監督の『ある用務員』で、伊澤は福士誠治演じる用務員兼ボディーガードと闘う女子高生の殺し屋、シホを演じ、「オモテの顔」としての映画デビューを飾った。そこから今作の主演に抜擢である。
金髪のショートヘアで中性的な雰囲気の「まひろ」は、普段は干物のようにソファに寝転がり、コミュ障のためバイトの面接も全滅、話し方にも覇気がない。それが殺しの現場では、突如体がしなやかに動き、ボクサーのような闘志で目に光がみなぎる。本物の殺し屋はこうやってオーラを変えているのではないかと妄想したほどだ。
伊澤は、アクションシーンで「自分がこう見られたい」というよりも、シーン全体で自分がどうしたらうまく立ち回れるかしか考えていないように見える。それがよりシーンをエンタメ的「リアル」に感じさせてくれた。つまり、ワクワクした。
アクションも当然ながら体で表現される演技だ。今後も映画人として、多様な顔を見せながら国内外で活躍してほしい。(安田佑子)
批評家コメント
不思議な女優である。等身大でどこにでもいそうな、それでいて得体の知れない、いまどきの女の子。その姿がスクリーンに写し出されても、当初は強烈なインパクトは残さないが、物語の進行に合わせて次第に目が離せなくなり、終にはその儚げな魅力の虜となる。
芝居こそが我が人生。若くしてそんな印象を与える女優。
石川瑠華は1997年、埼玉県で生まれる。2017年から女優としての活動を開始。翌年に公開された『きらきら眼鏡』でスクリーン・デビュー。その後、『希望のゆくえ』『イソップの思うツボ』と立て続けに主演する。
今回の受賞の対象となった『猿楽町で会いましょう』(児山隆監督)では、ひたむきで一直線、だれもが手を差し伸べたくなるような純朴さを身にまとい、それでいて実は嘘だらけのヒロインを演じ、淡い光と濃い影との奇妙なコントラストを巧みに写し出している。男たちの愛やら欲望やらを時にはひょいとかわし、時には全身で受け入れるしたたかな一人の女の人生が浮かび上がる。
同じく2021年に封切られたウエダアツシ監督の『うみべの女の子』では、憧れの先輩に手痛くフラれ、その腹いせで衝動的に同級生に体をゆるす中学生を演じている。愛のない二人のセックスはいつのまにか生活の一部になっていく。この作品での演技でもまた文句なしの存在感を見せつける。
これらの作品(共にR15+)で石川瑠華は、華奢でいたいけな肉体を惜しげなくスクリーンに焼き付け、青春の不条理と戸惑いを体現する。
この先もどんな困難な役柄でも果敢にチャレンジする女優として、引っぱりダコになるに違いない。現実に5本の主演作が企画され、進行していると聞く。今後の活躍がさらに期待される。日本を代表する演技派女優に育って欲しいと願いつつ、またそうなるべく可能性を充分に秘めた逸材であると信じて疑わない。(島敏光)
批評家コメント
青春キラキラムービー、時代劇、SFがごちゃまぜになった松本壮史監督の『サマーフィルムにのって』は、正に魅力あふれる若手俳優の宝庫といえる。それぞれの演技者たちが、自分の立ち位置を把握し、イキイキと輝いている。
なかでも時代劇オタクの女子高生に扮した伊藤万理華の個性が際立っている。ベビーフェイスと落ち着きを同居させ、シーンごとにくるくると変わる表情。そのヴァリエーションには舌を巻く。喜怒哀楽を分かりやすく表現するが、決して大袈裟にもわざとらしくもならない。天性の資質か後天的に培われたものかは不明だが、そねみ、ねたみ、苛立ちなどの負の感情でさえもキュートに見せてしまうところが、女優としての比類なき強みとなっている。
伊藤万理華は1996年に大阪に生まれて神奈川で育つ、ということは、この映画の撮影時には優に二十歳を超えていたことになる。高校三年生を演じるのはキツかったのではないかと思わせるが、全くそんなことを感じさせないのは、童顔のおかげか卓越した演技力によるものか……。
4歳でバレエを始め、モデルを目指した少女は2011年、乃木坂46一期生のメンバーとなり、2017年には惜しまれつつ卒業。すでにその時、卒業の理由の一つに「女優になる夢」を掲げていた。
乃木坂46に在籍中の2015年にはホラー映画『アイズ』、2021年には短編映画『息をするように』に主演し、高い評価を受ける。その他『賭ケグルイ』をはじめ、映画、テレビ、さらには舞台と、ノージャンルでの活動を続けている。
一方では、イラストレーターとしての仕事、雑誌の連載もこなし、さらにはPARCOで独自の個展も開催したと聞く。なかなか一筋縄では行かないベビーフェイスである。
伊藤万理華はこの映画を大きなキッカケにして、令和の時代を駆け抜ける先頭集団の一角に躍り出た。今後の活躍から決して目を逸らすことはできない。(島敏光)
批評家コメント
「か、まま、け」(津軽弁で「さぁ、ご飯、食べなさい」という意)。
西川洋子だからこそ演じられた役に違いない。『いとみち』の主人公「いと」(駒井蓮)と西川が演じた祖母・ハツヱの津軽弁と津軽三味線の対話は愛おしい。思春期のいとが出かけようとすると、ハツヱは「け(食べな)」と紐にぶらさがったままの裸の干し餅を持たせようとし、いとに嫌がられても気にしない。
演技は初めてという西川に、自然体なのに素人らしからぬオーラがあるのは津軽三味線の名人として人前で長年演奏をしてきたからだろう。しなる親指、三味線の棹(さお)を舞う左手。連(つれ)三味線でいとを優しく導く笑顔は、名人としてではなくハツヱそのものだ。
西川は津軽三味線の名人・高橋竹山の最初の弟子として16歳から三味線を始めた。奏者としての名は「高橋竹苑」。「西川洋子」は地元青森でテレビやラジオに出演する時に使っていた名前だ。
青森市文化団体協議会文化功労賞、青森市教育文化顕彰を受賞。また青森市内では郷土料理と民謡を供する店「甚太古(じんたこ)」を母の代から引き継ぎ、2019年、68年間切り盛りしてきた営業を終えた。
『いとみち』は青森・津軽を舞台に、メイドカフェで働く女子高校生「いと」の奮闘記。
「糸道」とは、三味線や琴を弾く技能を指すとともに、三味線奏者が弦との摩擦から左人さし指の爪先にできる溝のことを言うそうだ。
コロナ禍による撮影延期、クラウドファンディングでも支援を募りながら19日間で撮影。横浜聡子監督はじめ、主演の駒井も西川も青森出身で、言語は津軽弁を貫いた。思った以上に聞き取れないのも面白く、今作の魅力的なアイデンティティとなった。第16回大阪アジアン映画祭では日本映画で初めてのグランプリ、そして観客賞を受賞した。
西川は、今作で自分の撮影がクランクアップした時に、「間の大事さっていうのは三味線でやってきたはずですが、あらためて(演技も)間の大事さを感じました」と話した。青森に頼もしい74歳の新人俳優がいることを多くの人に知ってもらいたい。(安田佑子)
批評家コメント
『すばらしき世界』は、佐木隆三の長編小説『身分帳』を原案に、西川美和監督が自ら脚本化した秀作。これまでの監督作ではオリジナル脚本にこだわり、ストーリーテラーとしての力量を遺憾なく発揮した西川監督だが、原作ものだとどう出るのか。作品を拝見する前は、その一点のみが気になっていた。だが、さすが西川監督。小説を原案にしても、彼女の世界はすばらしきものだった。
『蛇イチゴ』『ゆれる』『ディア・ドクター』『永い言い訳』……などなど。そのどれもが、大なり小なりの罪を犯す人、という主人公が描かれていた。それが今作では、罪を犯し刑期を終えた主人公がたどるその後の人生、というアプローチ。
罪を犯すに至る心の道程はそれぞれあれど、社会のアウトサイダーである彼らを「人」として描くことに注力してきた西川監督。社会から隔絶された刑務所で人生の大半を過ごして出所し、社会復帰の場面で幾度となく壁にぶちあたる元殺人犯の三上を描くために、これまでにはなかった取材を大量にこなした。それは、刑期を終えた人や彼らを取り巻く環境を知ることだけでなく、原作にある「裏」を探る旅だったに違いない。
ゼロから物語を構築し、自分ごととしてこれまでの作品を作り出してきた西川監督には、原作があること自体が重圧だったろう。だが、テーマ設定、キャスティング、取材で得た知識と経験、その全てが相まって、原作があると感じる瞬間がまったくない「西川色」の傑作に仕上げている。
稀代のストーリーテラーとしての才能を思う存分発揮した西川監督を心からたたえたい。 (よしひろまさみち)
批評家コメント
今回は編集賞ということだが、実のところ、受賞作の『JUNK HEAD』では、編集のみならず、公式記録によると、監督、原案、キャラクターデザイン、撮影、照明、音楽、絵コンテ、造形、アニメーター、効果音、VFX 、声優などなど、映画作りの全てを一人でこなしてしまった堀貴秀監督。突然現れて天才的な仕事をなし遂げてしまった。まさに孤高のクリエイターという言葉に値するだろう。既成の作品からの影響をほとんど感じないという独創性も貴重な才能だ。
何より驚かされたのは、コマ撮りで全編が構成されたこの長編にあっても、作品自体が実にリズミカルに、生き生きと躍動していることだ。一秒24コマの画像をすべて撮影するという途方もない作業にも拘らず、この作品からは小気味の良い潔さが伝わってくる。
本作では撮影に際し、綿密な絵コンテを元にしたと聞くが、これは監督自身の頭の中に、それぞれのカット割りが明確に描かれていたということなのだろう。無駄なカットを撮らないというその潔さ。そこから導かれたよどみのない編集によって、『JUNK HEAD』という壮大にして荒唐無稽な一大叙事詩が生まれた。堀監督からは、怖いもの知らずの勢いとともに、なんとも映画的な素質が垣間見えて仕方がない。
本作は総コマ数約14万、フィギュアはすべて手作りという、気の遠くなるような作業を積み上げ、制作に要した時間は、無慮七年といわれる。とかくモーション・ピクチャーというと、実写との差別化を図るためか、ある種の決まりきったギクシャクした動きで表現されることが多い。しかし、本作でのフィギアの動きは、むしろ実際の人物の動きに近く、リアルで本当に生きているような、なめらかな動きをさせることに成功している。
本作品は全三部作の第一部にあたるという。すでに第二部の制作に着手していて、第三部までの構想も完成していることと思うが、今から三部作すべての完成が待ち遠しい。(山口正介)
批評家コメント
この映画には、幾種類もの美しさが宿っている。古い家の庭に咲く椿、ほかにも藤、紫陽花、ツワブキ、牡丹……四季折々の木々草花の美しさ。そこに暮らす、富司純子の演じる主人公の絹子と、シム・ウンギョンの演じる絹子の孫娘、鈴木京香の演じる絹子の娘。3人の女性たちを中心に紡がれていく、女たちの生き方もまた美しい。
『椿の庭』は、長年写真家として活躍する上田義彦の映画監督デビュー作であり、監督だけでなく、脚本・撮影・編集も兼ねている。構想15年。そこには、上田監督自身が感じてきたもの、記憶にあるものが映し出されているそうだが、そういった想いを書き留めておくきっかけ、脚本の原案になったものは意外にもシンプルなものだった。住んでいた家の近くの家が、気づくと無くなって、空き地になっていたことだった。その家に住む人と話したことはないけれど、なぜかその家のことが記憶にある。
その記憶が15年後に『椿の庭』として映画になったというわけだ。観客にとっては、絹子も、彼女の娘も孫娘も、この映画で初めて出会う人たちであるのに、まるで自分の記憶をたどっているかのような不思議な感覚になるのは、やはり上田監督自身がカメラを回しているからなのだろう。
上田監督は「写真は、閉じ込められた時間を見ている。うつろっていく表現は映画のなかでのみ起こりうる」と言葉にしているが、この映画における“うつろい”は、単なる季節のうつろいだけではない、もっと生々しいうつろいだ。その独特の視点にも驚かされる。美しさのなかには、花が枯れゆく美しさもあれば、息絶えた生き物の最期を切り取った美しさもあり、やがて、絹子自身が人生を終える瞬間へと繋がっていく。それもうつろいだ。
上田監督が映し出す美しさには、美しさの表も裏も何もかもひっくるめた美しさがあり、消えゆく美しさがあり、そして美しさがもたらす豊かさが残る。幾つもの美しさを教えてもらった。(新谷里映)
批評家コメント
本年度の特別賞(松永武賞)は小倉智昭である。多くの人は小倉智昭といえば、テレビのアナウンサーというイメージがまず頭に浮かぶかもしれない。しかしながら実は本当の映画人である。
筆者にとってもこのタイミングで日本映画批評家大賞のタイトルをお受取りいただけるのは、大変感慨深いものがある。それほど、小倉智昭という人間からは映画に対する愛情があふれているのだ。
いつの頃だろうか、確か80年代から90年代にかけて、小倉智昭がパーソナリティを務めていたラジオ番組で、彼は映画紹介コーナーをもっていた。映画への熱い想いがラジオから流れだしていたし、彼の語る映画の話は実に多くの人に届く“何か“を持っていた。
決して語り口が批評家のように巧みという訳ではない。しかし彼が映画を語れば、リスナーには確かにその映像が浮かんで観えていた。それほど、小倉智昭というパーソナリティは、彼自身の視点から映画を理解し、その作品を第一に語りかけていた。これはなかなかできることではない。映画への熱い想いがあり、その情熱がリスナーに響いていたのだ。
私もラジオで紹介された映画を観に、映画館に足繁く通ったことを昨日のことのように覚えている。映画好きな、文化に敏感な若者たちの、ある意味インターネットのない時代の貴重な情報源だったことはまぎれもない事実である。
普通のアナウンサーっぽくない、と言ったら失礼かもしれないが、映画作品を自らの言葉で語れることこそが稀有な才能であり、それをアウトプットできる人間はそういない。これはある面で我々も見習うことができれば見習いたいほどである。
実のところ、日本映画批評家大賞の発起人でもある水野晴郎が、選考委員に入ってもらいたいという話をしていた。それほど、小倉智昭が語る映画には彼独自の視点とともに、説得力があった。ラジオで映画を語れる人間。これは私が知る限り、愛川欽也と肩を並べ小倉智昭のふたりだけである。ご本人も驚いているかもしれないが、まさに特別賞にふさわしい人物だ。(日本映画批評家大賞機構事務局)
批評家コメント
まさに才能のかたまり。俳優、シンガー・ソングライター、作家、音楽プロデューサー、DJとどれを取っても人並み外れた能力を発揮。キッチリと爪あとを残す。さらにカードマジックの腕前もプロに引けを取らず、将棋は有段者。昭和の生んだ奇才中の奇才。それが荒木一郎。
1944年、東京に生まれる。女優である母・荒木道子の影響もあってか、わずか9歳で初舞台を踏む。高校時代から音楽に没頭。ラジオ番組のDJを務め、テーマソング「空に星があるように」(66)でレコード・デビュー。日本レコード大賞新人賞に輝く。同年「893愚連隊」で映画批評家賞の新人男優賞を受賞。’67年には「いとしのマックス」で紅白歌合戦に出演等々、その八面六臂の活躍には枚挙にいとまがない。
映画では『日本春歌考』(67)を代表作の一つに挙げる人も多い。当時の世相を反映し、学生運動にそっぽを向き、これといった目的もなくダラダラと日々を過ごす若者の屈折した姿を、くっきりと浮かび上がらせる。
荒木一郎といえば、自由気ままにスクリーンを泳ぎ廻っている感性の人、という印象が強いが、関係者の話を聞く限り、むしろその真逆で、カメラアングルから照明の効果までを正確に把握した上で綿密に演技を組み立てている。自然体としたたかな計算が絶妙なバランスで成り立っているのだ。そこには高度な技術も伴う。
日活ロマンポルノとしては初めてキネマ旬報のベスト10入りを果たした『白い指の戯れ』(72)では、スリのシーンをワンカットで実際に相手の内ポケットから財布を抜き取ってみせ、リアルな映像作りに成功している。
その後もメジャーな話題作から成人映画まで、独自のスタンスで幅広いジャンルの作品に出演、または音楽監修として携わっている。
果たして荒木一郎はこの先、どこに向かうのか、どこへも向かわないのか、全く想像が付かないが、どちらにしてもその唯一無二の存在感はいつまでも消えることはないだろう。(島敏光)
批評家コメント
富司純子主演の『椿の庭』が昨年の春に公開された。古めかしい日本家屋に孫娘と暮らす一人の女性。その着物姿での佇まい、さらにはその所作の美しさに思わず息を呑む。富司純子は古き良き日本文化の伝統と魅力を余すところなく体現する。
高校三年生の時にスカウトされた美少女は、藤純子としてまたたく間に売れっ子女優となり、『次郎長三国志』『十三人の刺客』『日本侠客伝』等、1963年から’68年にかけて、毎年、何と10本近い映画に出演を続ける。
そして、1968年に『緋牡丹博徒』にめぐり逢う。任侠映画において「女は添えもの」というイメージを覆し、うら若き乙女が先頭に立って戦うという姿は新鮮で衝撃的であった。藤純子の花札さばきの見事さ、立ち廻りのかっこよさ、そして何よりも白い肌に浮かび上がる「緋牡丹」の美しさが評判となり、すぐに続編が作られ、たちまち東映のドル箱シリーズとなる。この年から’72年までに8本の『緋牡丹博徒』シリーズが生まれた。その間、『日本女侠伝』シリーズ(5作品)の他、さらにはこの2つのシリーズに加え、20本以上の作品に出演し、多忙を極めていた。
1972年、人気絶頂の中、七代目尾上菊五郎との結婚を機に引退を決意。引退記念映画として公開された『関東緋桜一家』で終止符を打つ。
それから17年後の1989年、あまたの映画人の期待に応え、『あ・うん』で銀幕に甦る。その演技力は色褪せることなく、様々な映画賞にノミネートされ、その後は数年に一度の割合で『あ、春』『フラガール』『明日への遺言』など、良質な作品を選んで出演を続ける。
2007年・紫綬褒章、2016年・旭日小綬章を受章。
とてつもない本数の映画に、あでやかな着物姿で登場し、激しいアクションをこなしてきた国民的な大女優が、静けさのあふれる『椿の庭』で14年振りの主演を務め、将来を担う若手の演技者に交じり、その優雅で気品にあふれる姿を再びスクリーンに甦らせる。
映画ファンにとって、至福の一瞬である。(島敏光)